養育費の支払いについて連帯保証人をつけることができた事例
こんにちは、代々木駅徒歩3分、新宿駅徒歩9分の優誠法律事務所です。
今回は、夫が外国籍の女性と不貞の上、海外に渡航してしまい、離婚を求められた事案で、離婚後の養育費や慰謝料の支払いについて夫の父親に連帯保証をしてもらうことで解決した事例をご紹介いたします。
養育費や慰謝料について合意できたとしても、非監護親の経済力などから履行能力(支払能力)に疑問があるような場合もありますので、同様のことでお困りの方は、ぜひ参考にしていただければと思います。
事案の概要~不貞をした夫から離婚調停~
ご相談者Aさん(妻)は、ご結婚後ご主人Bさんとお子さん2人(いずれも当時小学生)をもうけ、ご自身もお仕事をされて、いわゆる兼業主婦として生活していました。
しかし、紆余曲折の末、Bさんがタイで生活したいと言ってご自宅を出て行ってしまう状況に至りました。
Bさんはタイで生活したい理由について色々とおっしゃっていたようですが、Aさんは、Bさんがタイの女性(Cさん)と親密な仲にあることを把握しておられました。
そうしたところ、Bさんから日本の裁判所にAさんを相手方として離婚調停が起こされ、対応に困ったAさんは当事務所にご相談に来られました。
(わざわざBさんが調停を起こしてきた理由の詳細は不明ですが、Cさんとタイで籍を入れるためにAさんとの離婚を成立させる必要があったのではないかと思われます。)
調停の経過~養育費と不貞慰謝料で合意~
Aさんは、Bさんからの調停申立てを受け、こちらから積極的に離婚したいわけではないものの、再度Bさんと家庭を築くこともできないとのお考えをお持ちでした。
そこで、当方からは、今回の別居はBさんの不貞行為により開始されていることから、Bさんはいわゆる「有責配偶者」であり、「Bさんからの離婚請求は認められない」、との反論を行いました。
このような主張は、仮に最終的には離婚という形で解決するとしても、その条件をこちらの有利にするために有用です。
Bさん側からは、Cさんとの関係が不貞行為には該当しないとの反論がなされましたが、日本でのAさんやお子さんとの同居を解消した直後にタイに渡航しており、その主張には無理がありました。
他方で、AさんとしてもBさんとの関係再構築は困難と捉えていましたので、Bさんの不貞を前提に、離婚をする方向で条件交渉を重ねました。
最終的に、婚姻費用額を超える養育費額(月額6万円弱)と、お子さんの習い事や私学費用の負担(別居後生じた費用については、離婚合意時に清算し、以後年2回精算)、別途慰謝料100万円という内容で離婚することに合意できました。
しかし、その時点でのBさんの貯蓄はあまり余裕のあるものではなかったため、慰謝料も含めて支払いを受ける予定の金銭の多くを離婚成立時に受け取ることができず、離婚後に支払いを受けるという内容で合意せざるを得ませんでした。
Aさんとしては、今回の別居開始の経緯からもBさんを信用しておらず、当然ですが、確実に支払いを継続させるための措置を求めたいとのご意向がありました。
そこで、Bさんのお父さんを連帯保証人とできないかという方向で動くことになりました。
養育費に連帯保証を付けることについての裁判所の対応
離婚の場面に限らず、一般に支払義務の履行を確実なものにするために、連帯保証という方法はよく用いられるところです。
連帯保証は、基本的には債権者と連帯保証人となろうとする人の合意があり、それを書面化すれば成立します。
(根保証の場合には極度額の明示なども必要になります。)
離婚の場面であっても、例えば慰謝料が分割払いとなった場合、その履行について連帯保証人をつけるということは比較的多くなされていると思います。
それでは、養育費に連帯保証人をつけることはどうでしょうか。
実は、養育費に連帯保証人をつけることについて、裁判所はかなり嫌がる傾向にあります。
理由としては、養育費は親だからこそ追う義務であり、主債務者である親が亡くなった場合には相続されないため、という説明がなされることがあります。
(個人的には、腑に落ちない部分があります。)
今回のケースでは、Bさんのお父さんからは、連帯保証人となることについての了解が取れました。
そのため、裁判所に対して、Bさんのお父さんを手続きに参加させ、連帯保証についても調停条項に盛り込みたい旨を上申しました。
しかし、裁判所からは、そのような調停条項をまとめることはできないとの回答がありました。
理由としては、上記の「養育費は親だからこそ負う義務」、という点とのことでした。
Bさんのお父さんも同意していることや、今回はBさんがタイに渡航していることで不払いとなった場合のBさんへの強制執行が奏功しない可能性が高いことなどもお伝えしましたが、裁判所の結論は変わりませんでした。
公正証書の作成
上記のとおり、裁判所が和解条項に養育費の連帯保証の条項を入れることを認めませんでした。
とはいえ、AさんとBさんとの間では概ね離婚条件は定まっており、連帯保証人を付けられないということのみをもって調停不成立とするのはもったいないと思われました。
そこで、Bさんのお父さんの連帯保証については、別途公正証書を作成する方向で動くことになりました。
そうは言っても、調停が成立していない以上、いくら合意はできているといっても主債務であるBさんの養育費債務は確定しておらず、主債務が確定していない以上Bさんのお父さんの連帯保証契約もその時点で作成することはできません。
他方で、何の手当もなく連帯保証を除いた調停を成立させ、その後にBさんのお父さんと連帯保証をしようとしても、その時点でBさんのお父さんが翻意して連帯保証契約を締結しないと言われる可能性もゼロではありません。
そこで、公証人の先生とも打ち合わせを重ねた結果、かなり特殊ではあると思いますが、
①AさんとBさんのお父さんとの間で、成立が予想される調停の内容を記載したうえで、その中のBさんの債務についてBさんのお父さんが連帯保証し、これについての公正証書を後日作成するとの内容の覚書を作成する。
②AさんとBさんの調停を成立させる。
③AさんとBさんのお父さんとの間で連帯保証公正証書を作成する。
という手順で進めることになりました。
これは、Bさんのお父さんとは①の中で公正証書作成を約束しているので、調停成立後に反故にはされないだろうということと、仮に万が一Bさんのお父さんが翻意して公正証書作成に協力しなかった場合でも、覚書の中で連帯保証の合意をしているので、公正証書がないとしても覚書の効力を主張できるということも考えた上での手順でした。
結論としては、③の公正証書作成までBさんのお父さんには協力していただき、無事に調停の成立と養育費についての連帯保証公正証書の作成を完了することができました。
仮にBさんの不払いがあったとしても、Aさんは連帯保証人であるBさんのお父さんに請求していくことができます。
このように、Aさんには離婚条件の実現についてご安心いただくことができました。
ただし、今回は結論として養育費についての連帯保証を付ける公正証書を作成することができましたが、これはいつでも作成できるというものではありません。
裁判所と同様、公証役場においても、養育費の連帯保証は原則避けるべきという考えがあり、それを認める特別の事情が必要とのことでした。
今回は、主債務者であるBさんが海外に居住しており、仮にBさんが不払いとなった場合にBさんに対する強制執行が奏功しない可能性が高いということを公証人に説明して説得しています。
養育費の連帯保証についての公証役場の基本的な考え方としては、債務者(今回はBさん)本人からの回収が実現できない事情が必要といって良さそうです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
離婚調停で条件を色々決めたとしても、それが実現されなければ意味がありません。
連帯保証という方法は、決めた条件の実現を確実なものにするためにしばしば用いられるものですが、それを養育費の場合にも用いることがあり得ます。
ただし、連帯保証について定めるには、手順をはじめ法的に困難な点があるため、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
優誠法律事務所では離婚の初回相談は1時間無料ですので、お気軽にご連絡ください。
優誠法律事務所公式HPはこちらから

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
よろしければ、関連記事もご覧ください!
【関連記事】
不貞相手と不貞配偶者それぞれから順次不貞慰謝料を獲得した事例
財産分与の解決事例~住宅ローン債務が残っている自宅に居住を続ける妻に対して、ローン完済後に所有権を移転することで合意~
住宅ローン債務が残っている自宅不動産がある場合の財産分与~離婚時に妻が連帯債務者から外れることができた事例~
投稿者プロフィール

2011年12月に弁護士登録後、都内大手法律事務所に勤務し、横浜支店長等を経て優誠法律事務所参画。
離婚や不倫に関するトラブルを多く担当してきましたので、皆様のお力になれるように、少しでもお役に立てるような記事を発信していきたいと思います。
■経歴
2008年3月 上智大学法学部卒業
2010年3月 上智大学法科大学院修了
2011年12月 弁護士登録、都内大手事務所勤務
2021年10月 優誠法律事務所に参画
■著書
交通事故に遭ったら読む本 (共著、出版社:日本実業出版社)
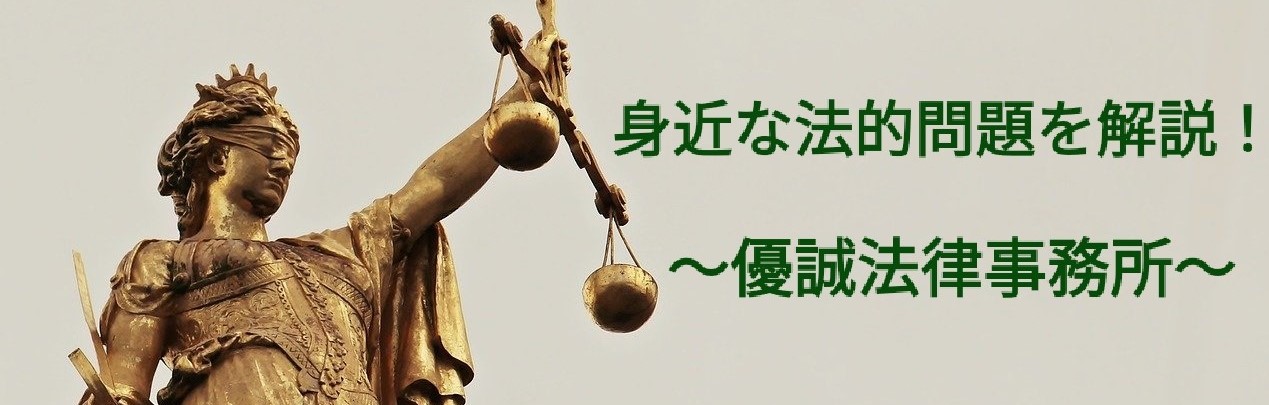
写真.png)







