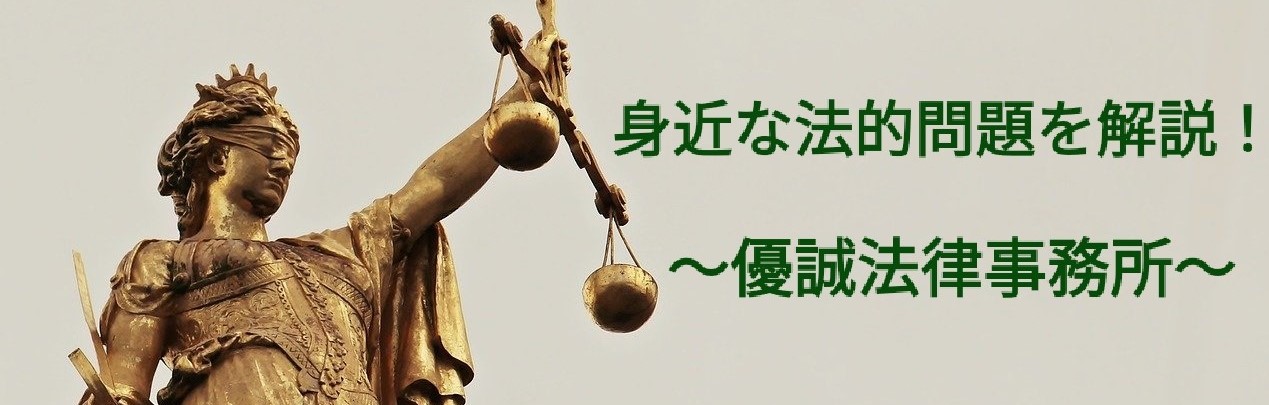有責配偶者とは?~不倫夫から離婚を求められた妻の対抗策~
こんにちは、代々木駅徒歩3分、新宿駅徒歩9分の優誠法律事務所です。
今回は、有責配偶者に関係する離婚問題について解説したいと思います。
離婚のご相談をお受けしていると、有責配偶者と評価されてしまうであろう方から離婚したいとのご相談をお受けすることがあります。
しかし、他の女性と不貞行為をしてしまった夫など、婚姻関係破綻の原因を作ってしまった側を「有責配偶者」といい、基本的に有責配偶者からの離婚請求は認められません。
もちろん、有責配偶者側が離婚を希望する場合でも、交渉で相手方配偶者が応じる場合もありますし、既に別居期間が長くなっていて未成熟子がいないなどの事情があれば、裁判でも例外的に離婚が認められる場合もあります。
配偶者が不貞行為をしている場合や、反対にご自身が不貞してしまったが離婚したいと考えている方などは、今回の記事を参考にしていただければと思います。
有責配偶者とは
「有責配偶者」とは、離婚・婚姻関係破綻の原因について責任のある配偶者です。
典型例としては、不貞行為が理由で離婚・婚姻関係破綻となった場合の不貞した側の配偶者が挙げられます。
DV事案におけるDVをした配偶者も有責配偶者です。
有責配偶者からの離婚請求
結論から申し上げますと、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。
民法770条1項は離婚理由について、以下のとおり定めています。
第770条1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
これらの事実は婚姻関係が破綻していることを示す事実であり、民法上は、このような状態を生み出した側からの離婚請求(有責配偶者からの離婚請求)が認められるか否かについては何ら規定がありません。
民法770条1項各号に定める事情があれば、その責任が夫婦どちらにあろうと離婚請求を認めるという考え方もあり得るところです。
しかし、裁判所はそのような考え方は採用しませんでした。
裁判所は、有責配偶者からの離婚請求は原則として認めないという立場をとっています(最高裁昭和62年9月20日判決等)。
(原則ということは例外もあるのですが、それについては下記で説明します。)
「有責配偶者からの離婚請求は原則として認められない」というルールは、離婚の交渉・調停・裁判の実務上、以下のような影響があります。
実務上の影響~相手方が有責配偶者である場合~
夫婦は、別居していたとしても、婚姻関係にある限り、他方配偶者の生活費や別居している子どもの監護にかかる費用を支払う義務があります(民法760条)。
これを「婚姻費用」といい、通常は「毎月●万円」という形での支払いとなることが多いです。
離婚すれば婚姻費用の負担義務はなくなり、子どもがいればその養育費のみの支払いとなります。
一般に、婚姻費用と養育費を比べると婚姻費用の方が高額になります。
したがって、毎月の支払金額のみで言えば、離婚後よりも離婚前の方が支払金額は高額になるケースが多いです。
これを実際の離婚事件に当てはめると、それぞれの考えはどうなるでしょうか。
例えば、A子さん(年収200万円)とB男さん(年収600万円)の5歳のお子さんがいる夫婦が別居を開始したケースで考えてみます。
裁判所の公表する算定表によれば、離婚前の婚姻費用の額は、毎月10万円から12万円程度になります。
他方で、離婚後の養育費の額は、毎月4万円から6万円程度です。
したがって、毎月の支払いについては、A子さんからすると離婚しない方が得、B男さんからすると早く離婚したほうが得、ということになります。
そのため、A子さんとしては、あえて離婚はせずに、毎月養育費よりも高額な婚姻費用を受け取ることを希望することがあり得ます。
他方で、B男さんとしては、高額な婚姻費用の支払いを早く終わらせるために早く離婚したいと考え、離婚についての交渉や調停、裁判を行うことになります。
ここで、例えばB男さんに不貞があってそれが原因で別居に至った、としたら、A子さんとしてはどのような行動に出るでしょう。
A子さんとしては離婚しない方が得なわけですから、有責配偶者であるB男さんからの離婚請求は認められない、と主張して、養育費よりも高額な婚姻費用の支払いを受け続けることができます。
あるいは、離婚には応じてもいいが、本来は(離婚しなければ)将来にわたって養育費よりも高額な婚姻費用を受け取ることができたはずなのだから、その分を考慮した解決金を離婚に際して払ってほしい、という交渉を行うことも考えられます。
以上のように、A子さんが離婚を希望する場合でも希望しない場合でも、相手配偶者であるB男さんが有責配偶者であると主張立証することにはメリットがあります。
有責配偶者側の対応
それでは、有責配偶者であるB男さんはどのように対応すべきでしょうか。
まずは、A子さんにも不貞があるのでこちらに婚姻関係破綻の主責任があるとは言えない、という主張や、そもそも不貞に至る前から婚姻関係は破綻していた、という主張があり得ます。
これらは、自分は有責配偶者ではない、という主張になりますが、実務上は結構多い印象です。
また、有責配偶者だからといって、絶対に離婚請求が認められないわけではありません。
裁判所は、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないとしていますが、例外として、
① 別居期間が長期間
② 未成熟子がいない
③ 離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない
という場合には、離婚請求が認められる余地があると判断しました(最高裁昭和62年9月20日判決)。
したがって、有責配偶者側としては、自分が有責配偶者であるとしても、上記の例外に該当すると主張していくことになります。
① 別居期間が長期間
同居期間や夫婦の年齢との比較で決せられます。
近年短期化が進んでいる印象はありますが、それでも5年から10年程度は必要ではないかと思われます。
② 未成熟子がいない
「未成熟子」というのは「未成年」とは少し概念が異なり、自分の資産や労力で生活する能力のない者をいいます。
したがって、18歳以上であっても、大学生などは未成熟子として扱うケースが多いです。
ただ、未成熟子がいないということを有責配偶者の要件として考慮すべきではないという見解もあり、実際、高校生のお子さんがいるケースで有責配偶者からの離婚請求を認めた裁判例もあります。
現在の実務上は重要な要素ですが、今後、絶対的な要件ではなくなっていくかもしれません。
③ 離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない
上記の昭和62年の最高裁判決では、「相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない」場合には離婚請求が認容される余地があるとされています。
「苛酷条項」などと言われることが多い部分ですが、ここでは、有責配偶者側が離婚までに十分な婚姻費用が払われてきたかという点や、有責配偶者側が離婚にあたって評価できる内容の慰謝料や財産分与などの申出をしているかという点などが考慮されます。
したがって、有責配偶者側としては、婚姻費用をしっかりと支払う、離婚にあたって金銭を支払う等の対応が必要になってきます。
有責配偶者側としては、以上①から③の例外に該当するために離婚請求が認められるという主張をしていくことになります。
まとめ
今回は、一方が有責配偶者であった場合の離婚問題について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
相手配偶者が有責配偶者であると主張立証することは、離婚を希望する場合でも希望しない場合でも、メリットがあります。
他方で、有責配偶者側としては、有責配偶者だとしても例外的に離婚が認められるケースに該当するとの主張立証を行う必要があります。
このように、有責配偶者であるか否かは、離婚問題に大きな影響があります。
ただし、私学や大学の費用の分担に関する近時の裁判所の考え方などから、必ずしも離婚をせずに婚姻費用を受け取り続けるのが良いとも言い切れなくなっている面もあります。
(私学費用等の分担については、以下の記事もご覧ください。)
この辺りも改めて別の記事で解説したいと思いますが、その点も含め、離婚をお考えの方は一度弁護士に相談されることをお勧めします。
優誠法律事務所では離婚の初回相談は1時間無料ですので、お気軽にご連絡ください。
優誠法律事務所公式HPはこちらから

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
よろしければ、関連記事もご覧ください!
【関連記事】
不貞相手と不貞配偶者それぞれから順次不貞慰謝料を獲得した事例
財産分与の解決事例~住宅ローン債務が残っている自宅に居住を続ける妻に対して、ローン完済後に所有権を移転することで合意~
住宅ローン債務が残っている自宅不動産がある場合の財産分与~離婚時に妻が連帯債務者から外れることができた事例~
投稿者プロフィール

2011年12月に弁護士登録後、都内大手法律事務所に勤務し、横浜支店長等を経て優誠法律事務所参画。
離婚や不倫に関するトラブルを多く担当してきましたので、皆様のお力になれるように、少しでもお役に立てるような記事を発信していきたいと思います。
■経歴
2008年3月 上智大学法学部卒業
2010年3月 上智大学法科大学院修了
2011年12月 弁護士登録、都内大手事務所勤務
2021年10月 優誠法律事務所に参画
■著書
交通事故に遭ったら読む本 (共著、出版社:日本実業出版社)