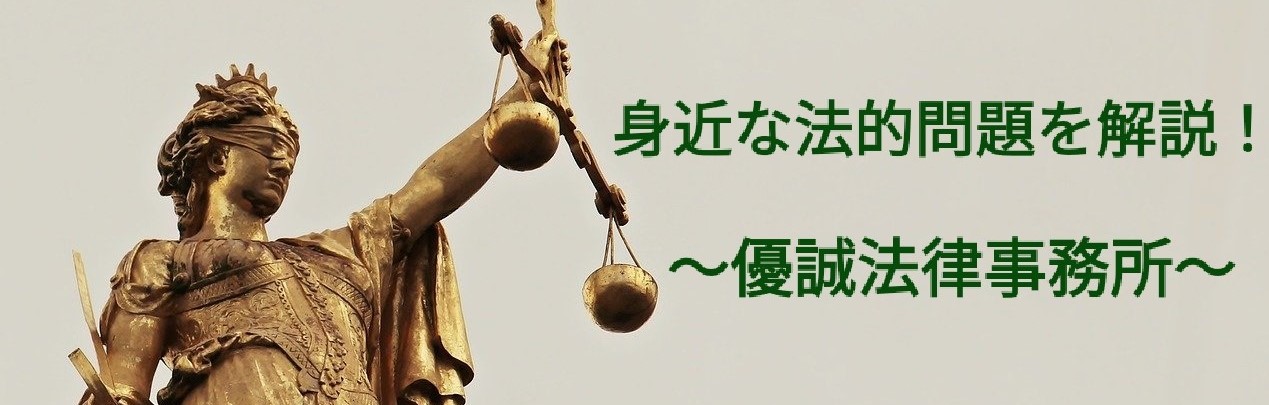住宅ローン債務が残っている自宅不動産がある場合の財産分与~離婚時に妻が連帯債務者から外れることができた事例~
こんにちは、優誠法律事務所です。
今回のテーマは、住宅ローン債務がある自宅不動産の財産分与です。
結婚や子供が誕生したことをきっかけに自宅を購入される方は多いのではないでしょうか。
実際、金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査/2023年」によると、2人以上の世帯の場合の持家率は全国平均で68.9%となっています。
また、本記事の公開時点では、住宅取得資金の贈与税の非課税制度を利用すれば、省エネ等住宅なら1000万円まで、一般住宅なら500万円までの贈与が非課税となり、節税効果の大きい特例も整備されているところです。
しかしながら、自宅を購入した後、夫婦の仲がこじれてしまい離婚という事態になった場合は、購入した自宅の清算をしなければなりません。
具体的には、不動産の財産分与です。その中でも住宅ローン債務がある自宅の財産分与については、様々な点に配慮しなければならないため、注意が必要です。
以下では、財産分与の場面で住宅ローン債務が残っている自宅をどのように処理するかという点をご説明します。
また、今回は、当事務所の弁護士が取り扱った事例のうち、依頼者である妻が住宅ローン債務の連帯債務者になっていたものの、相手方である夫と交渉した結果、連帯債務者から除外することができた事例もご紹介いたします。
住宅ローン債務が残っている自宅の財産分与
婚姻期間中(離婚前に別居している場合は別居時まで)に夫婦が取得した自宅は、一方の特有財産として取得したものを除き、その名義が夫又は妻のいずれであるかにかかわらず、実質的共有財産であり、財産分与の対象になります。
財産分与の具体的内容を検討するにあたっては、対象財産の評価を行っておくことが肝要です。
特に、不動産に関しては、非常に高額である上、金額も一義的に明らかなものではありませんので、自宅の査定は欠かせません。
また、自宅に住宅ローンが残っている場合、売却した際に、売却金でローンを完済できるのか(いわゆるアンダーローンなのか)、それとも、売却金ではローンが完済できないのか(いわゆるオーバーローンなのか)を見極めるため、住宅ローンの残高も確認する必要があります。
住宅ローンは債務ですが、夫婦共同生活のための資産の形成・維持に関連して生じた債務となりますので、こちらも財産分与の対象になることには注意が必要です。
そのため、住宅ローンにより自宅を購入し、住宅ローンが残っている場合、不動産の価額から住宅ローンを控除したものを財産分与の対象とすることになります。
自宅不動産がオーバーローンであった場合は財産価値をゼロとみなします。
やや応用的な話になりますが、オーバーローンの自宅以外にも財産分与の対象財産があった場合、オーバーしている債務部分を、自宅以外の対象財産に波及させるか否かが問題となることがあります。
例えば、財産分与の対象となる財産が、3000万円の自宅(住宅ローン4500万円)と、預貯金2000万円のみである場合を考えてみましょう。
まず、自宅不動産がオーバーローンであるため、自宅不動産の財産価値はゼロとみなします。
そして、オーバーした債務部分(1500万円)を自宅以外の対象財産に波及させないという見解を採用した場合、単に預貯金2000万円を半分に分割することになります。
一方、オーバーした債務部分(1500万円)を自宅以外の対象財産に波及させるという見解を採用した場合、預貯金2000万円からオーバーした債務部分1500万円を控除した500万円を半分に分割することになります。
どちらの見解を採用するかについては判断が分かれているところですので、場合によってはしっかりと主張していく必要があります。
また、オーバーローンの自宅を売却する場合には、住宅ローン債権者が自宅に設定している抵当権を抹消してもらうため、事前に住宅ローン債権者と交渉し、売却についての同意を得ておくことが必須です。
その他にも、住宅ローン債務がある自宅不動産の財産分与にあたっては、住宅ローン債権者のことを意識しておかなければならない場面が複数あります。以下もその一場面です。
住宅ローン債務者ではない者が自宅を取得する場合
住宅ローン債務がある自宅不動産について、住宅ローンの借主ではない配偶者が、「残りの住宅ローンを支払うので自宅を取得したい」と希望することがあります。
前提として、自宅を購入するために住宅ローンを組んだ場合、住宅ローン債権者である金融機関との関係では、借主である債務者(例えば夫)のみが住宅ローン債務を負うことになります。
離婚に際して、住宅ローンについて借主でない一方(例えば妻)が負担する旨の合意を夫婦間で行っても、それは夫婦間の内部的な取り決めに過ぎませんので、債権者である金融機関との関係では効力がありません。
そのため、離婚後、住宅ローンの負担を約束していた一方(妻)が住宅ローンを支払わなかったとしても、債権者である金融機関から支払いを求められるのは、あくまで借主である債務者(夫)のみになります。
借主である債務者(夫)としては、このような事態を避けるため、住宅ローンの負担を約束した一方(妻)に対し、債権者である金融機関と交渉して住宅ローンの借り換えをしてもらい、借主(夫)の債務を免責するよう求めることになります。
ただし、この方法を採用するためには、住宅ローンの負担を約束した一方(妻)に支払能力がなければなりません。
支払能力がなければ、通常、債権者である金融機関は、このような借り換えに応じないからです。
逆に、住宅ローン債務者(例えば夫)が自宅を取得する場合でも、もう一方(例えば妻)が連帯債務者や連帯保証人になっているケースでは、離婚の際に夫婦間で自宅を取得する住宅ローン債務者(夫)のみが住宅ローンを返済することに合意しても、債権者である金融機関との関係では自宅を取得しない連帯債務者や連帯保証人(妻)も債務を逃れることはできませんので注意が必要です。
以下では、このようなケースの具体的解決事例をご紹介します。
事案の概要~妻が住宅ローンの連帯債務者になっていた事例~
妻である依頼者Aさんは、夫であるBさんが他の女性との不貞関係を継続していたため、精神的な負担に耐えられなくなり離婚することを決意しました。
そのため、Aさんは弁護士に依頼し、夫であるBさんとの間で、慰謝料、財産分与及び養育費等の交渉を行うことになりました。
ここで問題となったのが、夫であるBさん名義の自宅不動産(オーバーローン)について、Aさんが住宅ローン債務の連帯債務者になっていたという点です。
離婚後、自宅不動産にはBさんが継続して居住することになっていたため、Aさんとしては、居住すらしていない不動産の住宅ローン債務を、離婚後も負担し続けることについては納得できないというご意向でした。
たしかに、今回のように、配偶者が住宅ローンの連帯債務者になっていて、当該配偶者が自宅を取得しない場合は、連帯債務者から除外するかどうか検討する必要があります。
ただし、当該配偶者を連帯債務者から除外するためには、ローン債権者である金融機関の承諾を得る必要があります。
とはいえ、例えば新たに連帯保証人を加えるといった事情がない限り、金融機関としては、当該配偶者を連帯債務者から除外することを承諾する可能性は低いです。
実際、Bさんの代理人弁護士からも、Aさんを連帯債務者から除外することは、金融機関との交渉を要する事項であるため、その点は留意してほしいとの回答がなされていました。
しかしながら、Aさんとしては、住宅ローンの連帯債務者から自身を除外するという条件については一切譲歩することができないとのご意向でしたので、粘り強く、Aさんを連帯債務者から除外するようBさん側に働きかけ続けました。
交渉の結果~妻が連帯債務者から外れることに成功~
最終的に、ローン債権者である金融機関は、住宅ローンを単独名義として組み直すための費用約250万円の一括払いを条件として、Aさんを連帯債務者から除外することに同意しました。
そして、話し合いの結果、上記の組み直し費用については、Bさんが全額負担することになりました。
その後、金融機関における手続は順調に進み、最終的に、Aさんは、Bさん名義の自宅不動産に関する住宅ローン債務の連帯債務者から除外されるに至りました。
また、離婚が成立し、不貞行為に基づく慰謝料として約350万円を獲得することができました。
Aさんとしても、この結果には大変満足された様子であり、納得した解決ができたようでした。
まとめ
今回は、住宅ローン債務が残っている自宅不動産の財産分与についてご紹介しました。
このような場合、自宅の資産価値を把握することから始まり、自宅を売却するのか維持するのか、維持する場合には誰が居住するのか、離婚後の住宅ローンはどちらが負担するのか、住宅ローン債権者に連絡する必要はないのか等、様々な点を考慮しなければなりません。
財産分与に限りませんが、離婚の話は夫婦仲が悪くなったために出てくる以上、離婚条件に関する話し合いは、直接当事者間で行うと感情的になり紛糾する可能性が高くなります。
そのため、代理人を通して話し合いをした方が、様々な面に配慮した冷静な話し合いをすることができることが多いといえます。
離婚条件についてお悩みの方は、弁護士に相談されることをお勧めします。
優誠法律事務所では、住宅ローン債務がある自宅不動産の財産分与を含めた離婚の初回相談は1時間無料ですので、お気軽にご連絡ください。
優誠法律事務所公式HPはこちらから

よろしければ、関連記事もご覧ください!
【関連記事】
財産分与の解決事例~住宅ローン債務が残っている自宅に居住を続ける妻に対して、ローン完済後に所有権を移転することで合意~
投稿者プロフィール

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。
■経歴
2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業
2011年3月 東北大学法科大学院修了
2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務)
2018年3月 ベリーベスト法律事務所入所
2022年6月 優誠法律事務所参画
■著書・論文
LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」