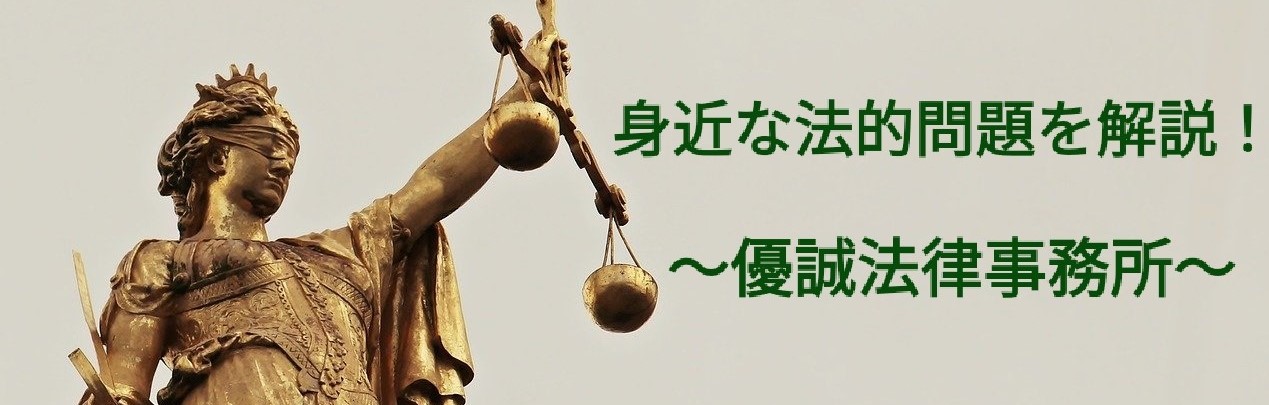離婚後に養育費を請求する方法を解説!
こんにちは、優誠法律事務所です。
今回は、離婚後の養育費請求について解説したいと思います。
離婚の際に養育費の取り決めをしたとしても、後に支払いが滞ることがあります。
また、離婚の際には事情があって養育費の取り決めをしなかったということもあります。
これらの場合であっても、養育費を諦める必要はありません。
今回の記事では、離婚後に養育費が支払われていない場合にどのような方法をとることができるか、について解説しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
離婚時に養育費の取り決めをしていたものの支払いが滞った場合
まずは相手方に連絡
離婚の際に離婚協議書を作成して養育費を取り決めていたり、離婚調停が成立してその中で養育費が決まっていた場合でも、養育費の支払いが途中で止まってしまうということは時々あります。
このような場合は、可能であれば、まず相手方に連絡をとって、養育費を支払うように申し入れます。
また、弁護士に依頼して、弁護士から相手方に支払うよう督促することも考えられます。
履行勧告と履行命令
離婚や養育費についての取り決めが、家庭裁判所の調停や審判、判決によってなされているにも関わらず、支払いが滞った場合には、家庭裁判所の「履行勧告」や「履行命令」という制度の利用が可能です。
履行勧告とは、家庭裁判所が、相手方に対して書面や口頭で養育費を支払うよう勧告する手続きです。
この手続きの申立てには費用がかからず、気軽に利用できる制度と言えます。
これに対して、履行命令とは、家庭裁判所が、相手方に対して養育費支払義務の履行を命じる審判を下す手続きで、相手方が理由なくこれに従わない場合には10万円以下の過料の制裁が用意されている手続になります。
こちらは申立費用が必要になりますが、制裁が用意されていることから、ある程度の実効性があると考えられる手続きになります。
強制執行
離婚や養育費についての取り決めが、判決や調停、審判、裁判所での和解であれば、強制執行という方法をとることができます。
公正証書のうち強制執行認諾文言(相手方が債務を履行しない場合に強制執行を受けても異議を述べないという文言)付きのものも、強制執行を行うことができます。
強制執行により、預金や給与の差押えを行います。
特に、給与については一度差し押さえてしまえば、相手が同じ勤務先に勤め続ける限り将来の養育費回収も可能となります。
ただ、強制執行をするためには、どこの銀行に預金があるか、勤務先はどこか等の情報を把握する必要があります。
差押え対象の預金や勤務先が不明な場合は、財産開示手続や情報取得手続というものを裁判所に申し立て、財産や勤務先を明らかにしていくことになります。
このあたりの手続きは近時法改正がなされ、実効性が強化されたり新たに創設されたものになります。
手続きとしては、必要書類の用意や差押え対象の特定など難しい部分もありますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
養育費調停の申立て
離婚や養育費についての取り決めが口約束にすぎない場合や、公正証書ではない離婚協議書でなされている場合は、養育費調停を家庭裁判所に対して申し立てます。
ここでの注意点は、養育費支払い開始の時点(始期)を口約束や協議書締結のあった離婚時とすることです。
通常、養育費調停を申し立てる場合の養育費支払いの始期は調停申立て時とされることが多いですが、口約束や協議書取交しが離婚時であるケースではその時点で約束自体はできていることから、離婚時にさかのぼっての支払いを主張する必要があります。
ただし、養育費の時効は5年ですので、養育費の取り決めが5年より以前の場合は、過去5年分の支払い(+将来の支払い)を主張することになります。
離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合
離婚時に養育費について決めなかった場合は、交渉あるいは調停で養育費の請求をすることになります。
この場合、請求を開始した時点が養育費支払いの始期とされるケースが多いため、早めに行動を起こす必要があります。
交渉による請求
元配偶者と連絡を取り、具体的な月額や支払日などを決めていきます。
請求自体は電話やメール、ラインなどでもできるのですが、できれば配達証明付きの内容証明郵便で請求を行うことをお勧めします。
というのも、仮に交渉がまとまらない場合には後述する調停を申し立てることになりますが、その場合、養育費支払いの始期が、「請求した時点」とされるケースが多いです。
配達証明付きの内容証明郵便であれば、養育費を請求するという内容の書面がいつ相手に到達したかが明確になるため、請求した時点について後に紛争になるリスクを回避しやすくなります。
元配偶者の現住所が不明な場合は、住民票を追いかける等の作業が必要になります。
これは、弁護士に依頼して進めることも可能です。
養育費調停での請求
交渉を行っても話がまとまらない場合は養育費調停を申し立てることになります。
交渉を挟まずにいきなり調停を申し立てることも可能です。
調停では裁判所を介して話し合いを進め、双方の合意ができれば調停成立となります。
双方の合意がまとまらなければ審判手続きに移行し、最終的には裁判所が養育費支払い義務の有無や金額について判断し、審判を行うことになります。
養育費はどのように決まるか?
養育費の算定にあたっては、裁判所の公表する養育費算定表が広く用いられています。
養育費は、基本的には両親の収入と子の年齢に基づいて算出しますが、この計算結果を表の形で見やすくしたのが養育費算定表です。
例えば、母を親権者として離婚したケースで、父の額面年収(給与)が600万円、母の額面年収(給与)が400万円、子が10歳の場合、月額養育費は4万円から6万円になります。
ただし、この算定表は、子が公立学校に通っていることを前提に作られています。
私立学校に通っている場合や大学に通っている場合には、算定表に考慮されている教育費と実際の支出額との差額を請求する必要があります。
この点についてはこちらの記事に詳しく解説していますので、ご参照ください。
また、ご覧いただければお分かりになると思いますが、養育費算定表では、養育費支払い義務者が給与額面年収2000万円を超える場合は算出できません。
この場合は、算定表を用いずに、標準算定方式と呼ばれる算定式に実際の収入等を当てはめて計算することになります。
もっとも、養育費額の上限については争いもあり、算定表の上限額で頭打ちとする考え方もあります。
このあたりは以下の記事で解説していますので、ご参照ください。
そのほか、給与収入と別で事業(自営)による収入がある場合も、算定表をそのまま用いることができません。
この場合は厳密には職業費分を控除する計算を行うことになりますが、算定表を基にどちらかの収入に揃えることで金額の算出ができます。
例えば、給与収入500万円と事業収入500万円がある場合、算定表上事業収入500万円に近い数字である496万円は、給与収入650万円と同等と評価されていますので、500万円と650万円を合算し、給与収入として1150万円の年収があると扱って算定します。
いずれにしても、お子さんが私学や大学に通っているケースや支払義務者の給与額面年収が2000万円を超えるケースなど、養育費算定表をそのまま使うことができない場合は、金額の算定が困難ですので、弁護士に相談されることをお勧めします。
まとめ
今回は、離婚後に養育費を請求する方法について解説しました。
養育費はお子様の成長に不可欠なものである一方、一度決めても支払いをないがしろにされたり、事情によって取り決めをしないまま離婚せざるを得なかったというケースを多く目にします。
養育費について泣き寝入りする必要は全くありませんが、他方で元配偶者がなかなか支払ってくれない、直接連絡を取りたくないということもあるかと思います。
そのような場合は、ぜひ一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。
優誠法律事務所では、離婚や養育費の初回相談は1時間無料ですので、お気軽にご連絡ください。
優誠法律事務所公式HPはこちらから

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
よろしければ、関連記事もご覧ください!
【関連記事】
財産分与の解決事例~住宅ローン債務が残っている自宅に居住を続ける妻に対して、ローン完済後に所有権を移転することで合意~
住宅ローン債務が残っている自宅不動産がある場合の財産分与~離婚時に妻が連帯債務者から外れることができた事例~
不貞行為の慰謝料請求は離婚後でもできる?不倫相手に請求した実例を法律事務所が解説
面会交流を弁護士に相談するメリットとは?離婚問題に強い法律事務所が解説
投稿者プロフィール

2011年12月に弁護士登録後、都内大手法律事務所に勤務し、横浜支店長等を経て優誠法律事務所参画。
離婚や不倫に関するトラブルを多く担当してきましたので、皆様のお力になれるように、少しでもお役に立てるような記事を発信していきたいと思います。
■経歴
2008年3月 上智大学法学部卒業
2010年3月 上智大学法科大学院修了
2011年12月 弁護士登録、都内大手事務所勤務
2021年10月 優誠法律事務所に参画
■著書
交通事故に遭ったら読む本 (共著、出版社:日本実業出版社)