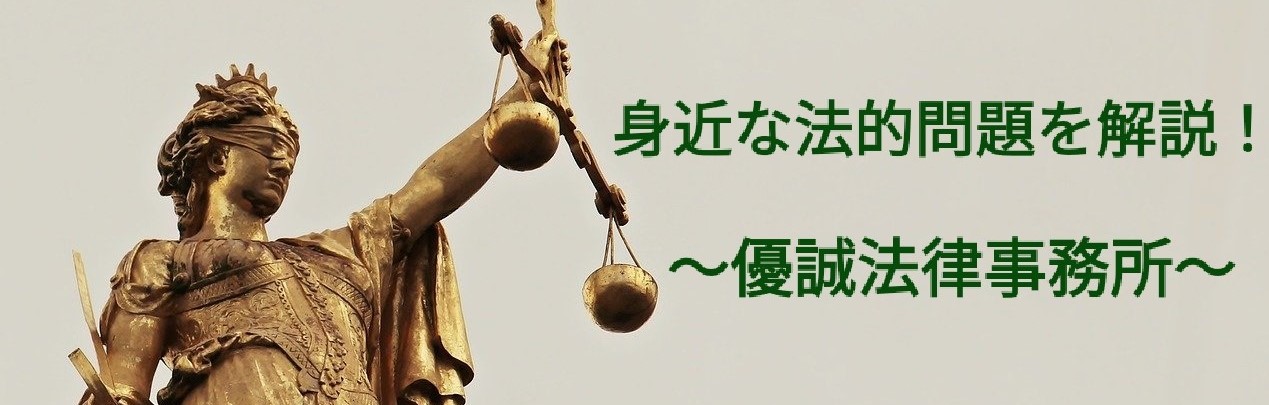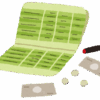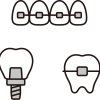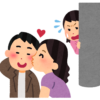離婚と財産分与は弁護士に相談すべき?|経営者・富裕層が知るべきメリットを総合解説
皆さん、こんにちは。
優誠法律事務所です。
今回は、経営者・富裕層の離婚について解説します。
離婚は誰にとっても人生の大きな転機ですが、経営者や富裕層にとっては単なる家庭問題にとどまらず、会社の存続や事業資産の維持に直結する重大なリスクとなります。
財産分与や慰謝料請求によって、築き上げてきた事業や資産に重大な影響が生じてしまうケースは少なくありません。
配偶者が株式を取得することで経営権が脅かされ、従業員や取引先にも不安が広がる可能性すらあります。
本記事では、経営者の離婚において特に注意すべき点と、事業資産を守るための具体的な対策を解説します。
離婚にあたって決めなければならないことを解説
離婚をする際には、感情的な問題だけでなく、法律的・経済的に整理しなければならない事項があります。
まずは、一般的に、どのようなことを夫婦間で決めなければならないのかという点を押さえておきましょう。
親権・監護権
未成年の子がいる場合、どちらの親が親権者となるかを決めなければ離婚を成立させることができません(民法819条1項)。
養育費
親権を持たない側が、子の生活費・教育費として負担するお金です。
家庭裁判所が定める「養育費算定表」(「標準算定方式」)に基づき、収入や子の年齢を考慮して金額が決められます。
原則として子が18歳に達するまで支払が続きますが、夫婦の学歴や生活水準によっては「大学卒業(22歳頃)まで」とする合意がなされることも多くあります。
親権や養育費は、子どもの生活や教育に直結する重大な事項です。
さらに、離婚後も子どもと会う権利を確保する『面会交流』の取り決めも重要になります。
面会交流の方法や頻度をめぐってはトラブルに発展することもあるため、早い段階で弁護士に相談し、適切な合意内容を決めておくことが望ましいでしょう。
養育費や親権、婚姻費用に関する具体的な事例・解説は下記の記事で詳しく紹介しています。
財産分与
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産は、名義にかかわらず原則として「共有財産」とされ、離婚時には一方から財産の分与を請求することができます(民法768条)。
分与の対象となるのは、預貯金・不動産・株式・退職金の一部などですが、この範囲や金額につき協議が調わないときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます(同条2項)。
そして、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定めます(同条3項)。
なお、結婚前から持っていた財産や相続財産は「特有財産」として分与の対象外になります(民法762条1項)。
財産分与について夫婦間の協議が整わない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
離婚調停では調停委員を介して話し合いが行われ、当事者の主張や証拠をもとに合意形成を図ります。
調停で合意できなければ裁判(審判)に進むこともあるため、弁護士が代理人として同席し、適切な主張を行うことが不可欠です。
「財産分与に関しては、不動産や住宅ローンの扱いが大きな争点となることもあります。実際の解決事例については、以下の記事も参考になります。
慰謝料
離婚の原因を作った配偶者(不貞行為やDV、悪意の遺棄など)に対し、精神的苦痛の損害賠償として請求できる金銭です。
必ず発生するものではなく、原因となる不法行為が存在する場合に問題となります。
慰謝料請求や不貞行為に関する具体的なケースについては、以下の記事も合わせてご覧ください。
年金分割
厚生年金に加入していた配偶者がいる場合、婚姻期間中の年金記録を分割する制度があります。
富裕層(経営者)の離婚の問題点
夫婦が離婚する際には、上記の点を決めていかなければなりませんが、経営者や富裕層の離婚には特有の問題が存在します。
(1)財産分与の範囲が広い
会社株式やオーナー借入金など、事業と密接に関係する財産まで対象となる可能性があります。
(2)事業運営への影響
配偶者に株式が渡れば、経営権や会社の信用に大きな揺らぎが生じます。従業員や取引先に不安を与えることもあります。
(3)養育費・慰謝料の高額化
慰謝料請求の金額や財産分与の額は、収入や資産規模によって大きく変動します。
相手から過大な請求を受けた場合でも、弁護士が適正な額を主張することで、法的に妥当な範囲に調整することが可能です。
高収入であるがゆえに、養育費や慰謝料の金額が高額になりやすく、適正額を主張できなければ過大な負担を負うことになりかねません。
有責配偶者にあたる場合、慰謝料や財産分与の条件が厳しくなる傾向があります。有責配偶者に関する解説は以下の記事をご覧ください。
事業資産を守るための具体的対策を解説
財産分与対象の明確化
財産分与の対象には、自宅不動産や投資用不動産なども含まれます。
不動産は、評価額の算定や名義変更の手続きに時間と費用がかかり、トラブルとなるケースが多い資産です。
特に経営者の場合、会社の事業用不動産が財産分与の対象となるかどうかが問題となることがあり、弁護士による専門的な整理が不可欠です。
会社の資産そのものは原則として分与の対象にはなりません。
しかし、経営者が個人として保有する株式は対象になり得ます。
重要なのは、結婚前から保有していた特有財産と、婚姻中に形成された共有財産を正確に区別することです。
株式評価の適正化
非公開会社の株式は、評価方法によって大きく金額が変わります。
– 類似業種比準法
– 純資産価額法
– 配当還元法
どの算定方法を採用するかで、数倍の差が出ることもあります。
専門的知識を持つ弁護士が関与しなければ、不利な評価方法で巨額の分与を余儀なくされかねません。
持株比率維持の工夫
株式が財産分与の対象となる場合でも、議決権制限株式や譲渡制限株式を利用することで、経営権を維持できる場合があります。
あらかじめ会社の定款を整備しておくことが極めて重要です。
婚前契約・ポストナプシャル契約
– 婚前契約(プリナップ)
民法755条に基づき、婚姻前に締結・登記すれば法的に有効です。事業資産や株式を分与対象から外す合意をしておくことが可能です。
– ポストナプシャル契約(婚姻中契約)
現行民法の夫婦の法定財産制度(民法762条)に反する可能性があり、残念ながら法律上は明確な効力を持ちません。そのため、婚姻中契約によって財産分与の範囲を限定することは困難ですが、財産分与の協議の際の事実上の資料として勘案できる場合があります。
事例紹介
事例1:株式分与を巡る紛争
ある中小企業経営者が離婚する際、配偶者が「非公開会社の株式の半分」を要求しました。
しかし、会社定款に「譲渡制限条項」があり、実際には譲渡困難であることを弁護士が主張。最終的に株式は譲渡せず、評価額の一部を金銭で精算する形で合意しました。
ポイント:定款整備と弁護士の交渉力により、経営権を失わずに解決できる場合があります。
事例2:会社資産を巡る誤解
夫婦共有財産と会社名義の預金(なお、会社は1人のみの株式会社)が混同され、相手方は「会社名義の資産も実質的には個人財産であり、財産分与の対象となる夫婦共有財産である」と主張。
しかし、弁護士が帳簿・入出金記録を精査し、会社資産と個人資産を明確に区分することに成功。会社資産は分与対象から除外されました。
ポイント:経営者が資産を混同しているようにみえても、弁護士が証拠整理することで事業を守れる場合があります。
事例3:高額慰謝料請求の調整
いわゆる有責配偶者であった経営者が、離婚時に慰謝料として1000万円を請求されました。
しかし、弁護士が収入構造(役員報酬、配当、経費等)を正しく評価し直すなどの交渉の結果、適正な水準に調整。支払額は当初請求額の半分以下となった事例があります。
弁護士に依頼するメリットを解説
経営者や富裕層の離婚事件は、複雑で高度な専門性を要します。
そのため、弁護士に依頼することで、正確な財産評価や調停への対応、裁判における適切な主張が可能となります。
経営者の離婚は、通常の離婚とは比べものにならないほど複雑で、事業の存続にも直結します。弁護士に依頼することで次のようなメリットがあります。
– 財産分与の対象を正しく区別し、不当な請求を防ぐ
– 株式評価額を適正に主張し、経営権を維持する
– 定款や株式スキームを用いて支配権を守る
– 慰謝料・養育費の過大請求を調整する
– 社外への影響(従業員や取引先)を最小化する
離婚や財産分与を巡る手続きには、弁護士費用や裁判所に納める費用が発生します。
調停申立ての手数料や、不動産評価・鑑定費用が必要となる場合もあります。
当事務所では費用の目安や支払い方法について事前に丁寧にご説明し、依頼者のご負担を軽減できるよう柔軟に対応しています。
優誠法律事務所の豊富な経験
当事務所はこれまで、経営者・医師・士業などのいわゆる富裕層に該当する方の離婚案件を数多く取り扱ってきました。
– 非公開株式の評価をめぐる交渉
– 高額資産の財産分与事件
– 婚前契約書の作成・アドバイス
– 事業承継と絡む複雑な離婚案件
「経営者の離婚」に特有のリスクを熟知しているため、依頼者の事業と人生の両方を守る解決策を提示できます。
まとめ
経営者の離婚は、財産分与・慰謝料といった経済的な問題にとどまらず、会社の経営権や事業資産の維持という重大な課題を含みます。
これらの対応は、専門的知識と交渉力を持つ弁護士のサポートなしには困難です。
優誠法律事務所では、経営者の離婚に関する豊富な経験をもとに、依頼者の大切な事業と資産を守るための最適な解決策をご提案します。
財産分与や慰謝料請求は、専門的な法律知識がなければ解決が難しい問題です。
特に高額資産や事業資産が関わるケースでは、早期に弁護士へ相談することが最も重要な一歩となります。
当事務所では、初回無料相談を実施しており、調停・裁判への対応も含めたトータルサポートを提供しています。
経営者等の方で資産を守りつつ離婚をしたい(やむなく離婚に応じたい)とお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。
優誠法律事務所公式HPはこちらから

投稿者プロフィール

これまで、離婚・相続・労働・交通事故などの民事事件を数多く手がけてきました。今までの経験をご紹介しつつ、皆様がお困りになることが多い法律問題について、少しでも分かりやすくお伝えしていきます。
■経歴
2009年03月 法政大学法学部法律学科 卒業
2011年03月 中央大学法科大学院 修了
2011年09月 司法試験合格
2012年12月 最高裁判所司法研修所(千葉地方裁判所所属) 修了
2012年12月 ベリーベスト法律事務所 入所
2020年06月 独立して都内に事務所を開設
2021年03月31日 優誠法律事務所を開設
2025年04月 他事務所への出向を経て優誠法律事務所に復帰
■著書
こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)