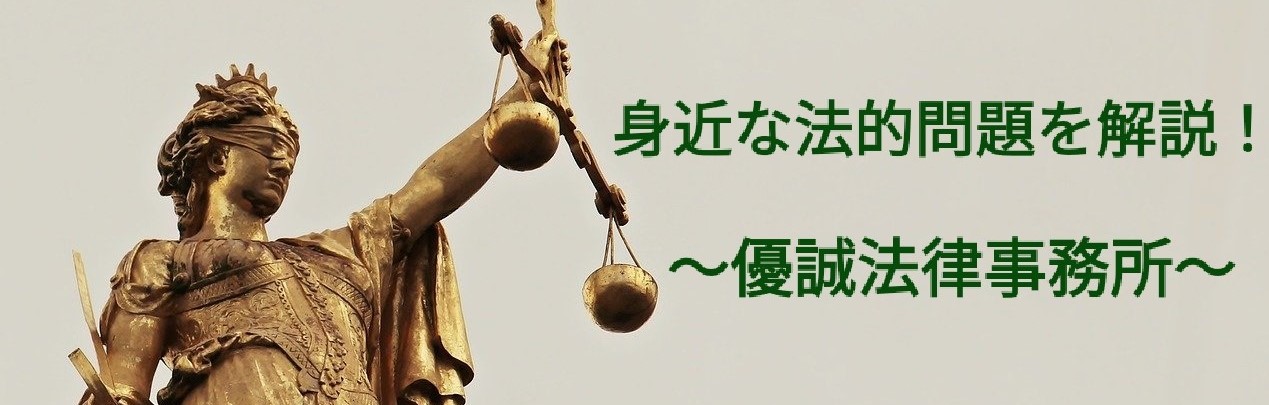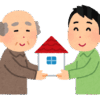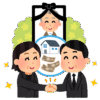遺産分割での使途不明金に関する高額解決事例
こんにちは、優誠法律事務所です。
今回のテーマは、遺産分割における使途不明金です。
遺産分割の話し合いをする過程において、被相続人名義の預金口座の通帳を見てみると、生前の多額の引き出しが判明することがあり、この場合、引き出しは誰が行ったのか、引き出したお金は何に使ったのかが大きな問題となります。
このような「使途不明金」については、被相続人の財産を管理している相続人が説明してくれれば良いのですが、何ら説明をしないことがあり、この場合、遺産分割の話し合いを進めることができなくなってしまうことがあります。
今回は、このような使途不明金について解説するとともに、当事務所の弁護士が取り扱った事例のうち、1000万円以上の使途不明金を回収できた事例をご紹介します。
使途不明金の問題
使途不明金の問題は、相続人が無断で、①被相続人の生前に、被相続人名義の預貯金を引き出す場合や、②被相続人の死亡後に、被相続人の預貯金を引き出す場合等に生じます。
また、被相続人と、被相続人と同居している相続人は近しい関係にある親族であるため、身内意識が働き、被相続人名義の預貯金の使途に関する客観的証拠が残されておらず、真相解明が困難となることが多くあります。
このような使途不明金の問題は、遺産分割に関連する付随問題であるものの、不法行為や不当利得の問題であることから、基本的に遺産分割の対象とはなりません。
もっとも、相続人全員が、使途不明金を遺産分割の対象とすることに合意すれば、遺産分割の対象に含めることは可能です。
今回ご紹介する事例においても、使途不明金を遺産分割の対象とすることについて、相続人全員が合意していたため、遺産分割協議の中で解決することができました。
使途不明金の請求手続
遺産分割の話し合いをする過程において、被相続人名義の預金口座から多額の引き出しがなされていることが判明した場合、まずは、被相続人の財産を管理していた相続人に対し、預貯金払戻しの経緯やその使途に関する説明を求めるとともに、開示すべき資料を開示するよう促していくことになります。
それにもかかわらず、被相続人の財産を管理していた相続人から、使途不明金に関する説明が満足になされない場合は、遺産分割調停や民事訴訟といった裁判手続を検討することになりますが、どの手続を利用するかについては非常に悩ましいところです。
遺産分割調停(家庭裁判所において合意を目指して話し合いが進められる手続)を申し立てた場合は、被相続人の財産を管理していた相続人を含む相続人全員が、使途不明金を遺産分割の対象とすることに合意しない限り、使途不明金を遺産分割に含めて解決を図ることができません。
そのことが理由で遺産分割調停が不成立となり、遺産分割審判(家庭裁判所における終局的判断の裁判)に移行したとしても、使途不明金は遺産分割の対象ではない以上、遺産分割審判においては使途不明金の問題を解決することはできません。
一方、民事訴訟(簡易裁判所や地方裁判所において判決によって紛争の解決を図る手続)として、不当利得返還請求訴訟や不法行為損害賠償請求訴訟を提起したとしても、被相続人の財産を管理していた相続人から、使途不明金について、被相続人からの生前贈与である旨の主張がなされて、この主張が裁判所に認められた場合、その限度で不当利得返還請求や不法行為損害賠償請求は認められないことになります。
被相続人からの生前贈与が特別受益に該当するとしても、仮に遺産分割審判が確定してしまっている場合には、蒸し返して特別受益の主張をすることができなくなります。
このように、使途不明金を請求するにあたり、どの裁判手続を利用するか検討する際には、戦略的な見通しを立てる必要があるのです。
今回の事案の概要~被相続人の口座から多額の引出し~
被相続人Aさんが亡くなり、相続が発生しました。
被相続人Aさんには子供であるBさん、Cさん、Dさんがいましたが、Dさんは被相続人Aさんが亡くなる前に亡くなっていました。
そのため、被相続人Aさんの相続人は、Bさん、Cさんと、Dさんの子供であるEさん・Fさん・Gさん・Hさん(以下「Eさんら」といいます。)でした。
被相続人Aさんの財産管理はBさんが行っていました。
Eさんらは、被相続人Aさんの生前、どのような財産管理が行われていたのかについては知りませんでした。
被相続人Aさんが亡くなった後、Eさんらは、財産管理を行っていたBさんから、遺産分割として、遺産について殆ど説明がなされることのないまま、Eさんら4名分として150万円を渡す旨の提案を受けました。
このような状況で、Eさんらは、Bさんの提案内容に疑問を感じたものの、どのように対応してよいかわからず、当事務所にご相談になり、そのままご依頼いただくことになりました。
被相続人Aさんの資産や収入状況を踏まえると、遺産分割として150万円という金額は少ないと思われたことから、まずはBさんに対して、被相続人Aさんの財産管理状況について説明するよう求めることにしました。
また、並行して、被相続人Aさん名義の預貯金について調査を行うことにしました。
そうしたところ、被相続人Aさん名義の預貯金から、高額の使途不明な金銭が多数回に渡りATMや窓口で引き出されていることなどが判明しました。
そのため、これらの点についてBさんに説明を求めたものの、納得できる説明がなされなかったことから、裁判外での解決は困難であると判断し、遺産分割調停を申し立てることにしました。
本件調停における争点~使途不明金~
調停では、被相続人Aさん名義の預貯金から、高額な金銭を多数回に渡り引き出していたのはBさんではないか、その使途が不明な金員(使途不明金)についてBさんに責任があるかが争点となりました。
Bさんは、一部について特別受益であることは認めたものの、それ以外の引き出しについては、被相続人Aさんから依頼されて引き出した上で、被相続人Aさんに現金で手渡したものである等と主張し、不法行為や不当利得の成立を否定しました。
しかしながら、被相続人Aさんは、生前、施設で生活しており、当該施設では現金や預貯金通帳の所持が禁止されていたことから、Bさんの上記主張は矛盾していました。
そのため、この矛盾点について指摘するとともに、預貯金口座の取引履歴と照らし合わせながら、裁判所に提出する主張書面において、被相続人Aさんから依頼された内容、被相続人Aさんの通帳の管理状況や通帳を入手した経緯、現金の受渡場所等を釈明するようBさんに求めました。
また、Bさんに対して、遺産分割調停が不成立になった場合、使途不明金について民事訴訟を提起する予定であることも伝えました。
本件調停の結果
その後、調停での協議の結果、最終的にBさんが大きく譲歩することとなり、もともと提案されていた150万円の遺産の他に、BさんがEさんらに対して使途不明金として1000万円強を支払う内容の調停が成立しました。
一般的に、使途不明金の請求は、客観的証拠が残されていないことが多く立証が非常に困難な類型ではありますが、遺産調査をしたり、資料精査をした上で、説得的な主張をしたことが功を奏したのだと思われます。
Eさんらとしても、この結果には大変満足された様子であり、納得した解決ができたようでした。
まとめ
上でご説明したとおり、使途不明金の請求をするにあたっては、遺産調査をした上で、戦略的な見通しを立てる必要があります。
非常に専門的であるため、これらのことを一般の方が行うのは、非常に困難かと思われます。
使途不明金の請求について相談されたいということでしたら、弁護士に依頼した場合の見通し等も含めて、お話しさせていただければと存じます。
優誠法律事務所では、使途不明金の請求を含めた相続の初回相談は1時間無料ですので、お気軽にご連絡ください。
優誠法律事務所公式HPはこちらから

よろしければ、関連記事もご覧ください!
【関連記事】
投稿者プロフィール

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。
■経歴
2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業
2011年3月 東北大学法科大学院修了
2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務)
2018年3月 ベリーベスト法律事務所入所
2022年6月 優誠法律事務所参画
■著書・論文
LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」