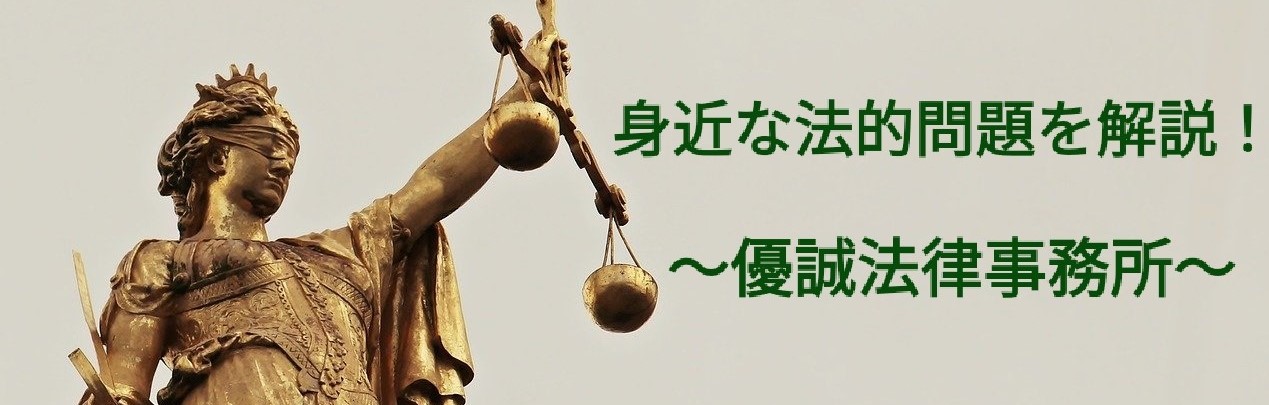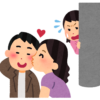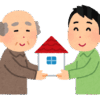実例で解説!遺産分割で兄弟が納得する不動産の分け方
皆さん、こんにちは。
優誠法律事務所です。
今回のテーマは遺産分割です。
相続において、遺産に含まれる不動産は、多くの家庭で遺産分割協議における最大の争点となりがちです。
特に、故人の財産が実家などの不動産一つしかない場合、複数の法定相続人の間、特に兄弟(姉妹)間で、「誰が引き継ぐのか」「どうやって公平に分けるのか」という問題が起こり、感情的な対立に発展することもあります。
このような相続における不動産のトラブルは、故人が生前に遺言書を作成していなかった場合に特に顕著になります。
当事務所は法律事務所として、これまで数多くの遺産分割のご相談を受けてきました。
その経験から言えるのは、不動産の分割は、単に法律や数字の問題ではなく、相続人それぞれの思い入れや感情が複雑に絡み合う、非常にデリケートな問題だということです。
ここでは、当事務所が実際に扱った事例を基に、遺産分割で兄弟姉妹が納得できる不動産の分け方について、具体的な解決策と、その円満な実現のための注意点を詳しく解説します。
遺産分割のスタートライン:知っておくべき3つの基本
遺産分割協議を始める前に、まず以下の3つの点を明確にすることが、後の話し合いをスムーズに進めるための鍵となります。
相続人の確定
故人の戸籍を辿り、誰が法定相続人であるかを正確に把握します。
認知している非嫡出子や、過去に縁を切ったと認識している兄弟も、法的には相続人となる可能性があります。
遺産の調査と評価
預貯金だけでなく、不動産、株式、借金、そしてゴルフ会員権や美術品など、すべての遺産をリストアップします。
特に不動産は、不動産鑑定士による鑑定評価や、複数業者による査定を行うことで、客観的な価値を把握することがトラブル回避の第一歩となります。
この評価額は、後の遺産分割協議における重要な基準となります。
相続分(法定相続分・指定相続分)の確認
法定相続分は民法で定められていますが、遺言書がある場合は、遺言書に記載された指定相続分が優先されます。
遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、遺留分侵害額請求という問題に発展することもありますが、その場合でも、まずは遺言書の存在を確認することが最優先です。
不動産を「分ける」3つの主要な方法
不動産の分割方法は、大きく分けて以下の3つがあり、これらを単独または組み合わせて用いることで、個別の事情に応じた柔軟な解決策を見出すことができます。
現物分割
不動産そのものを各相続人に配分する方法です。
例えば、「兄は実家を、弟は賃貸アパートを相続する」といった形です。
複数の不動産がある場合や、土地を分筆できる場合に有効です。
代償分割
特定の相続人が不動産を単独で相続し、その代わりに他の相続人に金銭を支払う方法です。
共有名義での相続を回避し、後のトラブルを防ぐことができるため、最も推奨される方法の一つです。
代償金の金額については、鑑定評価や複数業者の査定に基づき決定します。
換価分割
不動産を売却して現金に換えた上で、その現金を相続分に応じて分ける方法です。
最も公平で争いとなりづらい方法と言え、兄弟ともに不動産を必要としない場合や、代償金を支払う余裕がない場合などに有効です。
兄弟が納得した不動産分割の実例
ここでは、当事務所が実際に扱った事例を基に一部簡略化して、具体的な解決策と、その際に生じた課題、そして解決のポイントを解説します。
【事例1】 実家を巡る「代償分割」
・事案の概要
被相続人(父)が亡くなり、相続人は長男と次男の兄弟2人。
主な遺産は、東京都世田谷区の実家(土地・建物の評価額6,000万円)のみ。
長男はすでに独立して持ち家があり、次男が父と同居していたため、これからも実家に住み続けたいと希望している。
・課題
長男は、法定相続分である3,000万円相当の財産を受け取りたいが、次男は実家を手放したくない。
次男に代金を支払うだけの資金的余裕がない。
・解決策
このケースでは、代償分割を適用しました。
まず、複数業者からの査定を取得して実家の客観的な評価額を確定し、その金額について兄弟双方で合意しました。
次男には十分な貯蓄がなかったため、実家を担保に金融機関からローンを組むことを提案しました。
このローンで得た3,000万円を代償金として長男に支払うことで合意に至りました。
・解決のポイント
この事例では、事前に父が「次男に実家を相続させる」という公正証書遺言を作成していました。
これにより、長男も父の意思を尊重し、「弟が実家を守ってくれるなら」と理解を示し、スムーズに代償金を受け取ることに合意しました。
一方、次男も、長男の遺留分は4分の1ですが、実家をスムーズに相続できるのであればということで、長男に法定相続分相当額の代償金を支払うことに応じ、争族になることなく、遺留分を巡る紛争に発展することもありませんでした。
遺言書の存在が、感情的な対立を防ぐ上で重要な役割を果たしました。
【事例2】 複数の不動産を「現物分割」で円満解決
・状況
被相続人(母)が亡くなり、相続人は長男と次男の2人。遺産は、長野県の実家(評価額3,000万円。長男が将来住みたいと希望)と、評価額2,000万円の収益不動産(アパート)がある。預貯金は1,000万円。
・課題
不動産をどう分けるか。単純に兄が実家、弟がアパートを相続すると、価値に差が生じて公平ではない。
・解決策
このケースでは、複数の遺産を組み合わせる現物分割が有効でした。
遺産総額:3,000万円(実家)+2,000万円(アパート)+1,000万円(預貯金)=6,000万円。
法定相続分:兄3,000万円、弟3,000万円。
分割方法:遺産分割協議の結果、兄が実家(3,000万円)を単独で相続し、弟が収益不動産(2,000万円)と預貯金(1,000万円)を相続することで合意しました。これにより、兄弟それぞれの取得分が3,000万円となり、公平な分割が実現しました。
・解決のポイント
この方法の最大の利点は、不動産を共有名義にしないことです。
共有名義は、将来の売却や建て替えの際に、共有者全員の同意が必要となり、トラブルの原因となることが少なくありません。
将来を見据えたこの提案が、兄弟双方の納得を得る決め手となりました。
このケースでは不動産と預貯金で現物分割が可能でしたが、種々の財産を合わせても公平にならないケースでは、上記の代償金を組み合わせて解決することもあります。
【事例3】 誰も不動産を相続したくない場合の「換価分割」
・状況
被相続人(父)が亡くなり、相続人は兄と妹の2人。遺産は、広島県の実家(評価額4,000万円)のみ。
父は生前独居で、兄(福岡県)も妹(東京都世田谷区)も地元を離れてそれぞれの持ち家に住んでおり、実家に住む予定はない。
誰も不動産を単独で取得したいと考えていない。
・課題
不動産をどう分けるか。誰も引き取り手がない。
・解決策
このケースでは、換価分割が最善の選択となりました。
ステップ1(売却):まず、兄妹で協力して実家を売却しました。弁護士が仲介し、複数の不動産会社に査定を依頼し、最も信頼できる会社を選定しました。
ステップ2(費用控除):売却で得た代金から、譲渡所得税や仲介手数料、相続登記費用などの売却費用を差し引きます。
ステップ3(分配):残った現金を、法定相続分に従い、兄と妹で半分ずつ分けました。
・解決のポイント
換価分割は、相続人全員が金銭的に公平な遺産分割を実現できるというメリットがあります。
また、不動産の名義変更や相続登記の手間も一度の売却手続きで済ませることができ、手続きがシンプルである点もメリットです。
円満な解決のための弁護士からのアドバイス
上記の実例からわかるように、遺産分割を円満に進めるためには、以下の点が不可欠です。
感情的な対立を避ける:まずは感情的になりすぎず、全員が納得できる解決策を模索するための話し合いの場を設けることが最も重要です。
公平な評価の共有:不動産の評価額を兄弟間で共有し、その価値に全員が合意することです。不動産鑑定士の鑑定評価や複数業者の査定は、その強力な根拠となります。
専門家の活用:弁護士、司法書士、税理士などの専門家は、法律に基づいた公平なアドバイスを提供し、相続人間の話し合いを円滑に進める手助けをします。特に、遺産分割協議書の作成には専門知識が必要です。
遺言書の重要性:遺言書は、故人の意思を明確にし、相続争いを未然に防ぐ最も有効な手段です。元気なうちに公正証書遺言を作成しておくことを強くお勧めします。
遺産分割は、故人との最後の思い出をどう形にするかという、非常にデリケートな問題です。
しかし、適切な手順を踏み、専門家のアドバイスを受けながら、感情的にならず冷静に話し合うことで、相続人同士が納得する形で円満に解決することができます。
もしお困りの際は、当事務所までお気軽にご相談いただければと思います。
初回のご相談は無料でお受けしております。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、他にも相続問題に関する事例をご紹介しておりますので、よろしければそちらもご覧ください。
投稿者プロフィール

2011年12月に弁護士登録後、都内大手法律事務所に勤務し、横浜支店長等を経て優誠法律事務所参画。
離婚や不倫に関するトラブルを多く担当してきましたので、皆様のお力になれるように、少しでもお役に立てるような記事を発信していきたいと思います。
■経歴
2008年3月 上智大学法学部卒業
2010年3月 上智大学法科大学院修了
2011年12月 弁護士登録、都内大手事務所勤務
2021年10月 優誠法律事務所に参画
■著書
交通事故に遭ったら読む本 (共著、出版社:日本実業出版社)