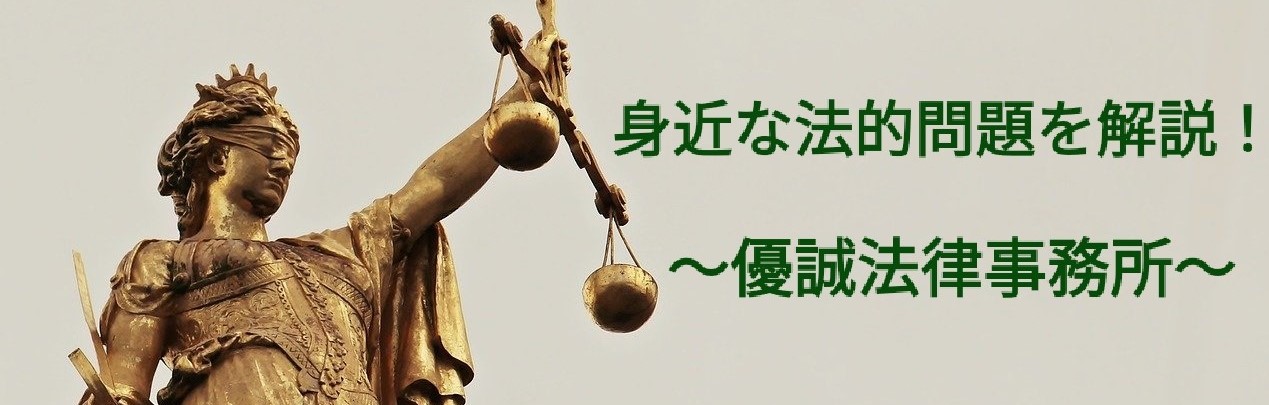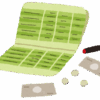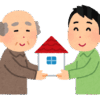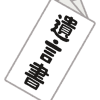遺産相続における不正行為とは?事例と法的対処法を解説
こんにちは、代々木駅徒歩3分、新宿駅徒歩9分の優誠法律事務所です。
相続は、人生の中でも大きな節目の一つです。
故人の遺された財産をどのように分けるかは、家族の絆を再確認する機会となるはずですが、現実には不正行為やトラブルが発生し、深刻な対立を招くことも少なくありません。
特に、遺言書の偽造や預金の使い込み、相続人の隠蔽行為などは、法的な問題に発展するリスクが高く、冷静かつ適切な対応が求められます。
本コラムでは、実際に起きやすい不正行為の具体的な事例や、万一トラブルに巻き込まれた場合の法的対処法・証拠の集め方・予防策まで、幅広く解説していきます。
相続を「争続」にしないために、今から備えておくべきポイントを解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
遺産相続における不正行為の種類と事例
遺言書の偽造や改ざんについて
「遺言書」は、亡くなった方の最終意思を反映する法的な書類であり、相続財産の分配において非常に重要な役割を果たします。
特に不動産やお金などの重要な財産を「誰に残すか」を決める手段として多く利用されます。
しかし、その重要性ゆえに、故意に偽造や改ざんが行われるケースも報告されています。
たとえば、手書きの遺言書(自筆証書遺言)の署名を他人が模倣したり、遺言の一部を削除・追加するなどの改ざんが行われることがあります。
また、遺言書の存在を隠して登記を自分名義に進めようとする悪質な事例もあります。
このような遺言の偽造・改ざんなどの不正な行いが発覚した場合、家庭裁判所に遺言の無効確認の申立てを行うことができます。
偽造や改ざんが証明されれば、遺言書は無効となり、法定相続に基づく相続が行われます。
なお、故意に偽造や改ざんをした相続人については、相続人の資格を失うケースもあります。
不正の原因としては、「財産を独占したい」という詐欺的な動機が多く、不動産など高額な資産が絡む場合に発生しやすい傾向にあります。
こうした行為を防ぐには、公正証書遺言の作成や、相続開始前に法的な対策を講じておくことが重要です。
もし遺言書に不審な点がある場合は、早めに専門家へ相談し、必要な書類の確認と法的な流れを理解することが、トラブル回避の第一歩となります。
相続人の隠蔽や虚偽の申告
相続人は、被相続人の死亡後、財産を受け継ぐ権利とともに、正確な申告義務も負います。
ところが、中には通帳や口座情報を隠す、預金を少なく申告するなど、虚偽の申告を行う相続人も存在します。
たとえば、同居していた相続人が、他の相続人に無断で金銭を引き出し、その存在を「知らなかった」と主張するケース。または、被相続人の死亡後に資産を隠し持ち、相続税の申告時に本来の金額よりも少なく報告するケースもあります。
これらの不正行為が発覚すると、税務署からの追徴課税や罰則が科されることがあります。
さらに、他の相続人との間で訴訟に発展する恐れもあります。
不正を防ぐ対策としては:
– 被相続人の資産や口座を生前に第三者も含めて共有する
– 相続開始後は金融機関へ連絡して口座を凍結し、残高証明書の請求を行う
– 相続税の申告は、税理士など専門家の確認を受ける
など、自己判断で進めず、透明性を保った手続きを意識することが大切です。
資産を隠さず申告する姿勢が、信頼関係を保ち、円滑な相続を実現します。
遺産の不正使用や使い込み
遺産の不正使用とは、相続人や関係者が遺産を無断で本来の目的以外に利用する行為を指します。
代表的な例は、相続手続きが完了する前に、遺産口座から多額のお金を使い込んでしまうケースです。
たとえば、親の死亡後、遺産分割協議が行われる前に、一部の相続人が勝手に不動産を売却して残高を移動させる、あるいは高額な生活費や趣味に遺産を充ててしまうなどが該当します。
これは、他の相続人の権利を侵害する不正行為です。
こうした行為が発覚した場合、民事訴訟によって損害賠償を請求できる可能性があります。
不正使用を未然に防ぐためには:
– 相続財産の全体像を一覧化し、関係者全員で共有する
– 相続財産を一時的に凍結して使い込みを防止する
– 相続手続き中は利用の範囲を明確に限定する
相続は感情的なトラブルに発展しやすいため、相続人同士の信頼関係を維持しつつ、適切に活用するルールを決めておくことが重要です。
知らぬ間に起きる使い込みを防ぎ、相続全体の信頼性を保ちましょう。
不正行為が発覚した場合の法的対処法
遺産分割協議の取り消し手続き
遺産相続では、相続人同士が集まり遺産分割協議を行い、財産の分配について合意することが一般的です。
しかし、その協議の過程で不正な合意があった場合には、取り消すことが可能です。
たとえば、ある相続人が事実を隠していたり、他の相続人を欺いて合意させた場合、その協議は取消しの対象となる可能性があります。
取消しをするためには、まず当初の協議内容を確認し、取消しの理由(詐欺、強迫、重大な錯誤など)を明確にします。
その後、協議の取り消し手続を進めるために、以下の準備が必要となります。
– 相続関係を証明する戸籍謄本
– 遺産の目録や土地・預貯金に関する書類
– 不正を裏付ける証拠資料
– 遺産分割協議書(原本)
取消しが認められれば、もとの協議内容は消滅し、再度協議を行う必要があります。
なお、20年の経過により時効となる場合もあるため、できるだけ早期の対応が求められます。
また、既に売却や登記が行われている資産がある場合は、さらに複雑な法的対応が必要になるため、専門家の助言を得ながら手続を進めることが重要です。
不当利得返還請求の方法
不正によって相続財産を不当に得た相続人に対しては、「不当利得返還請求」という法的措置を講じることが可能です。
この請求は、本来受け取るべきでない財産を受け取った者に対し、その財産の返還を求めるものです。
たとえば、ある相続人が被相続人の死亡前後に預貯金を勝手に引き出した場合、それは明らかに不当な行為であり、返還の対象になります。
返還請求を行う際は、まず以下の点を確認しましょう
– 引き出しが行われた理由の妥当性
– 金銭の移動を裏付ける通帳や振込記録の写し
– 不当利得が発生した時点と金額
– 他の相続人との財産分配の状況
また、返還請求の前に「請求権の消滅時効」についても確認が必要です。
不当利得返還請求は、「もらえる」ものではなく、「取り戻す」ものです。
時効が近い場合などは、内容証明郵便などで時効を中断するなど法的な手続きを踏んでいくことが望まれます。
訴訟を起こす際の注意点
不正行為に対して話し合いや請求による解決が難しい場合、最終的には訴訟を検討することになります。
ただし、時効があり、一定期間を過ぎると法的措置が提起できなくなるため、早期の対応が肝心です。
相続関連の訴訟で多く利用されるのが家庭裁判所です。
ここではまず「調停」を申し立て、当事者同士の合意を目指します。
調停が不成立となった場合、訴訟へ進むことになります。
訴訟を起こす際の準備としては:
– 不正を裏付ける証拠(通帳、録音データ、登記簿など)
– 被相続人と相続人の関係を示す書類
– 弁護士との事前相談(無料相談も活用可能)
– 裁判所への申立て書類の提出方法と提出期限の確認
こうした訴訟には費用や時間もかかるため、事前にメリット・デメリットを整理し、法的手段を最後の選択肢として活用することになります。
遺産相続における不正行為の証拠収集
証拠の種類と収集方法
不正行為を立証するためには、さまざまな記録や資料を確実に押さえる必要があります。
遺産相続においては、以下のような証拠が特に有効です。
– 株式や不動産の登記情報
– 相続人間のやりとりに使われたメール
– 相続財産に関する通帳や取引履歴の記録
– 遺言書や遺産分割協議書などの法的な資料
– 相手に送付した内容証明郵便
これらの証拠は、「どのような不正行為が、いつ、誰によって行われたか」を明確にするための基礎となります。
特にメールやLINEなどの電子的な記録は、言った・言わないの水掛け論になりがちな相続問題において、重要な意味を持ちます。
証拠の収集方法としては、自分でできる範囲の調査を行いつつ、以下のようなステップを踏むと効果的です。
1. 通帳コピーや不動産登記簿の写しを取得
2. 相手とのやりとりは、必ず記録として残す
3. 重要な主張は内容証明郵便で相手に通知
4. 法務局や金融機関に問い合わせて、必要な情報を揃える
5. 必要に応じて専門家の調査を依頼する
また、状況を整理し、証拠をまとめる際は、主張の要点を簡単にまとめた「証拠一覧表」などを作成しておくと、弁護士などに相談する際にも非常に有効です。
専門家の助けを借りるメリット
相続トラブルにおいては、自分だけで対応するには限界がある場面も多く、専門家の知識と経験を活用することで、より有利な状況を作り出すことが可能です。
法律の知識がないまま独自の判断で動いてしまうと、証拠不十分や手続きミスによって不利益を被るリスクがあります。
専門家に相談することで、トラブルの原因や本質を整理しながら、状況に応じた戦略を立てることができます。
特に、次のようなケースでは専門家の関与が大きなメリットとなります
– 相続財産の全体像が不明な場合
– 相続人間で強い争いがある場合
– 相手が既に弁護士をつけている場合
– 自分の取り分が少なくなっていると感じる場合
専門家と一口に言っても、それぞれに得意なカテゴリがあります。
たとえば、相続税に強い税理士、交渉や民事訴訟に慣れた弁護士、不動産登記を得意とする司法書士など、それぞれの知識を組み合わせることで、より良い解決が可能になります。
最近では、東京都23区内を中心に、地域に特化したサービスを展開する専門家も増えており、たとえば渋谷区や千葉方面など、地域事情に詳しい事務所を選ぶことで、より的確なアドバイスを気軽に受けられることもあります。
さらに、無料相談を行っている事務所も多く、費用を抑えながら専門的な意見を得られるという点でも安心です。
「自分で解決するには限界がある」「誰かにこの悩みを聞いてほしい」と感じた時点で、気軽に専門家に説明を求めることが、円満解決への第一歩です。
不正行為を防ぐための対策
遺言書の適正な作成
相続トラブルの多くは、遺言書の不備や不明確な内容によって引き起こされます。
したがって、遺言書は法律上の成立要件を満たした上で、適正に作成することが最も重要です。
遺言書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。
– 遺言者が自筆で書いた遺言は、全文・日付・署名が必要(自筆証書遺言)
– 公正証書遺言を選べば、法的な不備を防げる
– 配偶者や子どもなど法定相続人の相続権を無視した内容は、遺留分侵害のリスクあり
また、遺産分配の公平性を考慮し、生前贈与や生命保険の契約内容も含めて、財産全体の計算を行っておくことが望まれます。
たとえば、特定の相続人に住宅や名義変更済みの不動産を渡していた場合、それが必要以上に偏っていないかを検討する必要があります。
遺言書には作成時期に制限はありませんが、意思能力が低下する前に作成しておくことが必要です。
内容の変更が必要な場合は、新しい遺言を作成することで以前の内容を取り消すことができます。
正確な書き方や形式については、専門家に相談することで法的リスクを回避しやすくなります。
相続人間のオープンなコミュニケーション
相続人同士の信頼関係が希薄であると、不信感やトラブルに発展しやすくなります。
そのため、相続手続きは全員が納得できる形で進めるためにも、オープンなコミュニケーションが不可欠です。
まずは、兄弟姉妹や親族など、関係する全員が集まる話し合いの場を設け、相続内容を丁寧に説明することが大切です。
その際、誰か一人が勝手に進めるのではなく、本人の意見を尊重し、わかるように丁寧な説明を心がけましょう。
また、資産の詳細や進行中の取引の状況についても、可能な限り明らかにして情報をシェアすることで、相手の理解を得やすくなります。
特に、不動産や金融資産が複数あるケースでは、事前に情報を整理してから話し合いを進めるとスムーズです。
さらに、全てが全国共通という訳でもありませんので、地域の事情や法制度に配慮した進め方を選ぶことも重要です。
信頼できる専門家の選定
相続の手続きやトラブル対応において、信頼できる専門家の選定は極めて重要です。
専門家には、弁護士・税理士・司法書士・行政書士など、それぞれ得意分野がありますので、自分の課題に最適なプロフェッショナルを選ぶことが成功の鍵となります。
知人や親族からの紹介を受けられれば、信頼性の高い専門家に依頼することができますが、インターネットで探す場合には、口コミや専門家の実績一覧などを確認し、依頼内容に基づく対応が可能かどうかを見極めましょう。
特に以下のような点を確認するとよいでしょう。
– 相続・信託・税務に関する監修経験が豊富
– 明確な報酬体系を持ち、説明が丁寧である
– 地域密着型で相談しやすい
– 高齢者の相続や遺言に詳しい
– おすすめの専門家リストやメディア掲載歴がある
また、選び方を間違えてしまうと、費用ばかりかかって成果が出ないという事態になりかねません。
そのため、事前に依頼目的を特定し、それに基づいて判断することが重要です。
特に、資産規模が大きい場合や、複雑な信託が絡むケースでは、信託実務に強い専門家を選ぶことをおすすめします。
事案の概要~不正な引出行為だとして不当利得返還請求を受けた事案~
今回は、相続人が2名(兄弟)のケースで、一方の相続人がもう一方の相続人に対して、被相続人(亡父)の財産について、生前の不正な引出し・使い込みがあったと主張していたケースをご紹介します。
この事例では、不正な引出し・使い込みがあったと主張されていた相続人の方からご依頼を受け、最終的に不正引出に対する不当利得返還請求と遺産分割を一挙に解決することができました。
相続で争いが起きる場合、様々な争点が発生してしまうことも多く、事案によっては、遺産分割調停などの家庭裁判所での手続きだけでなく、地方裁判所の民事訴訟など、いくつかの手続きを経なければならないこともあります。
今回の事例は、遺産分割協議が必要であった上に、相手方から不正引出に対する不当利得返還請求訴訟も起こされましたが、結果的に一つの手続きで解決することができましたので、同様のことでお困りの方の参考になるかと思われます。
また、将来相続が発生したときにトラブルにならないように、ご両親を介護されている方が注意しておくべきポイントにも触れていきます。
裁判での反論・立証活動
本件のような被相続人の生前の預金引き出しの主張に対しては、以下のような反論を行うことが多いです。
・引出行為に関与していない
・被相続人が預金を引き出すのを補助したに過ぎない
・引出行為後に被相続人本人に交付した
・引出行為後に被相続人本人のために使った
本件では、依頼者のYさんは、被相続人のAさんと同居しており、ある時期以降はAさんの通帳を預かって管理するようになったのですが、使い込みと指摘される預金の引き出しの中には、Yさんが通帳を預かる以前のものも含まれていました。
したがって、この部分については、引出行為に関与していない、との反論を行いました。
ただ、引出行為に関与していないとの反論に対しては、相手方から被相続人が預金引き出し時点で既にご自身で動ける心身の状態でなかったとの再反論や、被相続人の口座からの引き出しと同時期に当事者の口座に近似する金額の入金がある等の再反論がなされることが多いです。
そのため、そのような点について問題はないか、Yさんに念入りに確認をしたうえで反論を行いました。
一方、YさんがAさんから通帳を預かった後は、引出行為自体はYさんが行っていました。
ただ、引き出したお金は、体を悪くしていたAさんのための自宅のリフォーム工事であったり、日々の通院やAさんの食費等生活費に充てられたものでした。
したがって、この部分については、引出行為後にAさん本人のために使った、との反論を行うことになります。
幸い、リフォーム工事等の大きな出費に関しては、当時の領収書等が残っており、これによって立証ができました。
また、生活費については領収書を残していたわけではありませんでしたが、Yさんが一部期間について出納記録を付けているものがありました。
全期間について出納記録があったわけではありませんでしたが、記録のある期間から1か月分の大まかな支出を計算し、これを全期間に引き直すという方法で主張立証を行うことができました。
以上の反論から、不正引出を主張された約5000万円の全てについてではないものの、概ね反論を行うことができました。
裁判所の心証と解決方法
そうしたところ、裁判所からは、2500万円の返還請求のうち、証拠関係を考えると300万円を返還するという内容で和解するのが望ましいとの和解案の提示がありました。
この提案は、Yさんとしては受け入れられるものであり、相手方からは反発もありましたが、最終的には合意することができました。
ただ、本件ではYさんから相手方への返還額が確定しても、まだ遺産分割協議が残っており、これを含めてどのように解決するかという問題が残っていました。
相手方が提起した本件の訴訟は不当利得返還請求事件というものですが、これは地方裁判所に提起されていました。
地方裁判所では、引き出した預金を返しなさい、という判断はできるのですが、その他の遺産をどのように分けるか(遺産分割)については判断できません。
遺産分割は家庭裁判所の管轄になります。
したがって、筋を通すのであれば、地方裁判所に提起された本件訴訟を和解によって解決した後、別途、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる、ということになります。
しかし、本件は、預金の引き出しの点が解決すれば、その他の遺産分割自体は当事者間の話し合いで解決が見込める事案でした。
他方で、地方裁判所では遺産分割はできず、不当利得返還請求訴訟を地裁で解決した後に再度遺産分割について話し合いを行うということも迂遠に思われました。
以上の状況から、訴訟外で遺産分割の内容を話し合いで決定し、その内容を地方裁判所の和解調書に添付して、和解の中で「別紙のとおり遺産分割がなされていることを確認する」という条項を入れてもらうことになりました。
これにより、不当利得返還請求事件と遺産分割を一挙に解決することができました。
まとめ:遺産相続における不正行為への対処法
早期発見と適切な対処が鍵
不正行為を未然に防ぎ、あるいは早期に解決するためには、相続に関する定期的なチェックが欠かせません。
たとえば、財産の内容や登記状況、通帳の動きなどを確認することで、不正の兆候を見つけやすくなります。
不正が発覚した場合には、すぐに対応を開始し、法的な対処を進めることが重要です。
最近の調査(2025年時点)によると、不正発生から5年以内に適切な対策を講じたケースの解決割合は非常に高いとされています。
逆に、時間が経過することで証拠が失われたり、相続人の一部が対応できなくなるケースもあります。
したがって、不正行為に対しては「早めの発見・早めの対処」が最も効果的な防御策であり、それが相続トラブルのリスクを最小限に抑える強い手段となるのです。
このコラムを参考に、今後の相続対策を改めて見直すきっかけとしていただければ幸いです。
専門家のサポートを受けることの重要性
不正行為が発覚した際、自分たちだけで問題を解決することは難しい場合も多く、専門家のサポートを受けることが解決への近道になります。
相続問題に精通した専門家は、過去の経験と知識に基づいて、適切な対応策をアドバイスしてくれます。
特に、相続財産の評価、分割方法、税務上の取扱いなど、専門的な知識が必要な場面では、第三者の視点が大きな力を発揮します。
たとえば、渋谷区など地域に特化した専門家を探すことで、地域の事情に詳しいアドバイスが受けられるほか、必要書類の取得や手続きの進行についても安心して任せることができます。
相続人の一人が介護を担っていたケースや、一部の相続人が生前贈与を受け取っているケース、遺産を受け取る権利自体に争いが生じている場合なども、法的視点で対象範囲を明確にしてくれる専門家の存在は極めて重要です。
不正行為への対応を成功に導くには、信頼できるパートナーを見つけることが鍵となります。
このまとめを通じて、「専門家に相談する」という選択肢を一つの武器として持っておくことを知るだけでも、今後の相続における不安を大きく減らすことができるでしょう。
相続に関して預金の不正引出を主張された、あるいは共同相続人が預金を不正に引き出している疑いがあるという方などは、まず弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
優誠法律事務所では相続のご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、他にも相続問題に関する事例をご紹介しておりますので、よろしければそちらもご覧ください。
投稿者プロフィール

2011年12月に弁護士登録後、都内大手法律事務所に勤務し、横浜支店長等を経て優誠法律事務所参画。
離婚や不倫に関するトラブルを多く担当してきましたので、皆様のお力になれるように、少しでもお役に立てるような記事を発信していきたいと思います。
■経歴
2008年3月 上智大学法学部卒業
2010年3月 上智大学法科大学院修了
2011年12月 弁護士登録、都内大手事務所勤務
2021年10月 優誠法律事務所に参画
■著書
交通事故に遭ったら読む本 (共著、出版社:日本実業出版社)