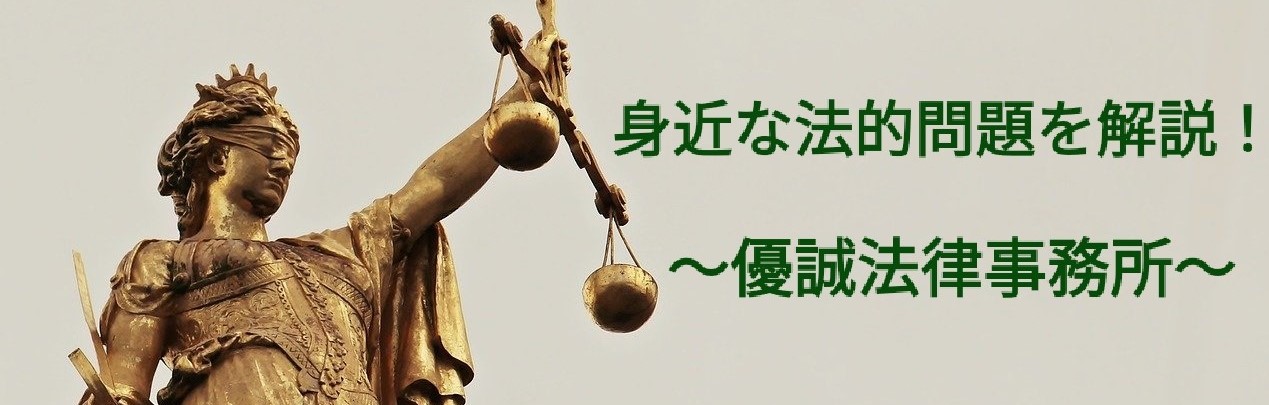未払賃金及び残業代の獲得に成功した事例~一方的な基本給の減額及び残業申請がないとの理由で残業代の支払を拒絶されていた事案~
皆様、こんにちは。
優誠法律事務所です。
今回は、製造メーカー会社の従業員が、勤務先会社から一方的に基本給を減額されてしまい、減額された未払賃金を請求した事例をご紹介します。
原則として、給与額などの労働条件は使用者が一方的に変更することはできませんが、今回の事例では部署異動などを理由に一方的に減額されていました。
また、今回の事例では、就業規則上、残業は事前許可制になっており、事前の残業申請がなかったという理由で残業代も未払いになっていました。
残業代について、事前申請が必要との理由で未払いになっているケースのご相談も時々お受けしますので、同じようなことでお困りの方は、参考にしていただけますと幸いです。
相談に至るまでの経緯等
今回の依頼者Aさんは、製造メーカー会社の営業職として入社しましたが、入社直後から営業のために必要であるとして、製造職の仕事に従事するよう指示を受けました。
その後、Aさんは、会社から今後も営業職ではなく製造職として勤務して欲しいとして部署異動の打診を受けました。
また、その際、Aさんは会社から、Aさんが入社した際の基本給の額は営業職を前提としたものであり、製造職に異動するのであれば基本給を減額すると一方的に告げられ、了承しないままに翌月の給与から基本給が減額されてしまいました。
その後Aさんが会社を退職することとなり、一方的に減額されてきた基本給の支払を求めることができないか、また、残業をしてきたにも関わらず残業代が支払われていなかった時期があったため、この支払いを求めることができないかなどを相談したいと思うようになり、弁護士に相談することにしました。
交渉(争点:基本給減額の有効性・残業申請の要否)
ご依頼後、担当弁護士において会社に対して請求を行ったところ、会社は、基本給の減額については、基本給ではなく営業手当の減給であり、営業職から製造職に異動したのであるから減額は当然であると反論してきました。
また、Aさんも基本給の減額を同意していたなどと主張をしてきました。
残業代については、就業規則において社長に対して残業許可の申請をしなければならないと定められているところ、Aさんの残業代については申請がなかったため支払わないなどと反論してきました。
会社側がこのような態度でしたので、担当弁護士が交渉では早期の解決ができないと判断し、Aさんは労働審判を申し立てることにしました。
労働審判とは
労働審判は、個々の労働者と事業主(使用者)との間の労働に関する紛争を、裁判所において迅速かつ適切に解決することを目的とした手続きです。
裁判官1名と労働関係の専門家である労働審判員2名で構成される労働審判委員会が、当事者の主張を聞き、証拠を検討し、紛争の実情に応じた解決策を提示します。
訴訟とは異なり、原則として3回以内の期日で審理が終結することを目指しており、迅速な解決が期待できます。
また、裁判所が紛争の実情に応じた柔軟な解決(和解による解決や、労働審判委員会による審判)を試みるのも特徴です。
労働審判の特徴のまとめ
迅速性:民事訴訟に比べて、早期の解決が期待できます。
専門性:労働問題に精通した裁判官と労働審判員が審理を行います。
柔軟性:和解による解決が重視され、紛争の実情に応じた解決が図られます。
出席:弁護士を依頼した場合、民事訴訟においては必ずしも裁判に出席する必要はありませんが、労働審判では早期の事案の把握の必要性等から、当事者の出席が求められます。
費用:訴訟に比べて、申立てに必要な費用が比較的安くなっています。
労働審判の流れ
申立て:労働者または事業主が、管轄の地方裁判所に労働審判の申立書を提出します。
第1回期日:原則として申立てから40日以内に、裁判所において第1回の労働審判期日が開かれます。
審理:原則として、第1回期日を含めて3回以内の期日で審理が行われます。
和解:審理の中で当事者双方が合意に至った場合、和解が成立し、手続きは終了します。
審判:和解が成立しない場合、労働審判委員会は、審理の結果に基づいて審判を下します。
異議:審判の内容に不服がある当事者は、2週間以内に異議を申し立てることができます。
訴訟移行:異議申立てがあった場合、労働審判事件は通常の訴訟手続きに移行します。
労働審判の審理期間
令和4年の司法統計では、労働関係訴訟による解決を図る場合、その解決まで平均的17.6か月の時間を要しますが、労働審判では平均81日での解決を期待することができるとされています。
そのため、交渉によって争点が明確になっている場合などでは、積極的に利用することが期待されます。
労働審判の結果~基本給減額分と残業代を獲得~
さて、Aさんの事案の舞台は交渉から労働審判の場に移りましたが、労働審判では裁判所(労働審判委員会)から各争点についてどのような見解が示されたのでしょうか。以下、解説します。
一方的な基本給の減額について
① 労働契約法での定め
労働契約法は、その第8条で「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」と定め、次条(第9条)では「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。」と定めています。
つまり、一度労働契約(雇用契約)で定めた労働条件については、原則として会社と労働者の合意がなければ変更することができず、例外的に要件を満たした就業規則の変更によってのみこれを変更することができるということになります。
② 今回の争点
今回、会社は、異動に伴う手当の変更であるとの主張をしていましたが、雇用契約においても就業規則においても営業職や製造職の手当の額については何らの定めもありませんでした。
また、Aさんの給与明細上、明確に基本給が減額されており、会社の主張には理由がないことは明白でした。
さらに、会社はAさんも減額について同意していたなどと主張していましたが、これを裏付ける証拠(例えば、減額された基本給が記載された新たな雇用契約書や雇用条件変更合意書など)はありませんでした。
③ 労働審判委員会の見解
上記の事情から、労働審判委員会としては、会社とAさんとの間には労働条件を変更する旨の合意があったとは認められず、その他Aさんの基本給が減額される理由はないとして、減額された基本給は未払賃金として会社が支払う義務があるとの見解を示しました。
残業代について
① 残業代の請求要件
残業代の請求は、労働の対価としての賃金の請求です。
そのため、残業代を請求するためには、労働者は会社の指揮命令下において労働に従事したこと、すなわち残業等の業務指示があることが前提となります。
② 今回の争点
今回の争点は、まさに業務指示があったかどうかという点でした。
会社としては、残業をするためには残業の許可申請が必要であり、これを許可することで業務指示を与えるのであるから、同申請がない残業は対価として賃金を請求することができる「労働」に該当しないというものでした。
この点、確かに会社が提出した就業規則には、会社の主張する内容の定めがありました。
しかしながら、Aさんはこの就業規則を一度も見たことがありませんでした。
また、Aさんは入社時に上司に対して残業について申請は不要であるのかを確認したところ、「不要である」との回答を受けており、入社後一度も残業の申請をしたことがありませんでしたし、他の従業員が同申請をしているのを見たこともありませんでした。
そして、Aさんはタイムカードを付けていましたので、会社はAさんが残業をしていることを認識していたにもかかわらず、残業の申請をするよう指示したことはありませんでした。
③ 労働審判員会の見解
上記の事情や、労働審判において、会社が残業申請用紙や他の従業員が提出した残業申請書などを提出しなかったことや、Aさんが残業申請をしていなくても残業代を支払っていた時期があったことなどを総合的に判断し、会社はAさんに対して残業代を支払う義務があるとの見解を示しました。
その判断理由は明確にはされませんでしたが、上記事情等から、就業規則の定めは形骸化されており、会社はタイムカードによってAさんの残業時間を把握していたにもかかわらず、これを放置しており黙示の業務指示があったととらえられたのではないかと思います。
労働審判での結果
最終的には、労働審判委員会からの見解を受けて、会社がAさんに対して180万円を支払うことで和解が成立しました。
まとめ
今回は、一方的に基本給を減額されてしまったことや残業申請がない残業代の請求に関する事案を紹介しました。
今回のように会社が賃金の支払いを拒否したとしても、会社の言い分が正しいとは限らず、未払賃金を請求することができる場合があります。
同じような状況の方は、一度専門家にご相談になることをお勧めします。
私たち優誠法律事務所では、残業代のご相談は無料でお受けしておりますので、是非ご相談ください。

優誠法律事務所公式HPはこちらから
よろしければ、関連記事もご覧ください!
投稿者プロフィール

これまで、離婚・相続・労働・交通事故などの民事事件を数多く手がけてきました。今までの経験をご紹介しつつ、皆様がお困りになることが多い法律問題について、少しでも分かりやすくお伝えしていきます。
■経歴
2009年03月 法政大学法学部法律学科 卒業
2011年03月 中央大学法科大学院 修了
2011年09月 司法試験合格
2012年12月 最高裁判所司法研修所(千葉地方裁判所所属) 修了
2012年12月 ベリーベスト法律事務所 入所
2020年06月 独立して都内に事務所を開設
2021年03月31日 優誠法律事務所を開設
2025年04月 他事務所への出向を経て優誠法律事務所に復帰
■著書
こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)